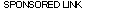チームを変えるか、ポジション変えるか
私は女だ。
性器ほど決定的なものはない。幼い頃、兄とその友人が裸で家を走り回っていた。私も一緒になって走った。けれどある日突然仲間はずれになった。「何で」と言うと「お前はチンコがないからだ」と言われた。
私は一緒に遊びたくて「ちんちん生えろ」と願った。立小便の真似をして、床をおしっこで汚し、母に叱られた。
いつだったかはわからないけれど、あるとき不意に気がついた。私は女で、男にはなれないのだ。
「トランスジェンダー」とも違う。トランスジェンダーなんていうと難しいが、つまりオナベ・オカマのことだ。私はそういったものとも違う。ゲイでもない。ただ、男になれない女であるだけだ。
「それはそれで苦しいのかな」
あるサイトで知り合った「ダリ」は、パフェを口に運びながら言う。「ダリ」は一見爽やかな美形の男子高校生であるが、その中身は「オカマでゲイです」ということだ。「ダリ」は海外の大学に進学するつもりだという。
「向こうのほうが、差別も大きいけれど、あけっぴろげでしょう。生きやすい気がするんだ」
たいした根性だと思う。私だったらまず海外に進学するということに尻込みをする。それとも彼――あるいは彼女は、海外に出て行く力に変換されうるような大きな苦しみを、これまでに背負ってきたのだろうか。
それに比べたら私の悩みなどちっぽけで、そして退屈なものだ。「女らしくない かわいげがない」自分の勇気と努力ひとつでなんとでもなるんだ。
男性に恋愛感情を抱いても「こんな女らしくない私は」と一歩引いてしまい、24にもなってお付き合いをしたことがない。幸い仕事はしているので年相応の貯金はあるが、「私でなければできない」仕事ではない。職業人としての私も、女性としての私も、非常に脆い。その思いを強くしたのが、性差をまさに人生のテーマとしている「ダリ」だった。
「ダリ」はファミレスの扉をくぐりながら言った。
「チームを変えることと、ポジションを変えること、みたいな違いかな」
出会った頃に私がもらしたサッカーの話を、覚えていたのだろうか。
琴子は教職についている。もっとも難しいといわれる中学生相手の商売だ。中学の頃の同級生だが、当時はあまり親しくもなかった。琴子はいつもお洒落で可愛かったし、恋愛なんかもずっとスムーズにしていた。田舎だったから、彼氏・彼女がいるのはごく少数だったけれど、彼女は中学3年のときには「少数派」になっていた。
その琴子と私が、一緒にご飯を食べたりするようになったのは成人式で再会してからだ。ご挨拶のように携帯の番号を交換して、社交辞令的に近況をたまにメールした。教職は辛いことも多いのだろう、琴子からのメールは就職1年目にぐんと増えた。「なぎさみたいに強ければなあ」そんなメールがたくさん入った。彼女は何を誤解しているのか。私は強くなどない。常に痩せ我慢をしているだけなのだ。それでも、愛らしい琴子のことを考えると無碍にもできず、「あんまり思いつめないで」とか「頭からっぽにするといいよ」なんてメールを親切ぶって返した。現在の関係は、それが功を奏したものだろうか。
たとえば、飲み会をしたらすぐに異性に話しかけられ、それでいて場を盛り上げることのできる琴子。異性には避けられて、場を盛り下げるだけの私。「一緒にいていいのかな」とたまに思う。
「ユキのお祝いさ」
話題を琴子が切り出した。そんなに親しくもなかった中学時代の知人が結婚し、先日出産したという。私たちもいつのまにかそんな年齢になったのだ。
「服でいいんじゃないかな。たくさんいるでしょ」
私と琴子はそれを共同で買う計画をしていた。3ヵ月後にも結婚式が2つある。出費は極力抑えたい。
食事を済ませて私たちはデパートのベビー服売り場に向かう。子連れでもない2人での買い物なのですぐに「お祝いですか」と声をかけられる。琴子は「先日生まれたんですって」とすぐ切り返す。そして、この柄可愛いんじゃないかしら。これ便利そう。靴下も可愛い。可愛いもの、綺麗なもの、が、女の子は好き。私は適当に相槌を打って、ああ、なんだか疲れたなあ。
「そういえばね」お店を出ると琴子が唐突に話題を変えた。この唐突さも「女の子らしい」。
「この前うちの部の子が、サッカー部の試合に出るっていうので、みんなで応援行ったのよ。サッカー部に比べたら下手っぴだけど、楽しそうだった」
へえ、と流した私の脳裏を、「ダリ」の言葉が蘇る。チームを変えることと、ポジションを変えること――。
「でね、見てたらね、なんだかなぎさを思い出した」
琴子は軽やかに笑みを浮かべ、こちらを向いた。その笑顔がまっすぐだったので、私はついつい目をそらした。
他者から見ても、サッカーと私はシンボリックに結びつくのだろうか。
近所に同じ年頃の女の子がいなかった。なので兄たちと遊んだ。まだJリーグもない時代である。サッカーより野球の方が人気だったが、兄たちはサッカーを好んだ。私はボールをただ蹴るだけだったけれど、楽しかった。その頃の私の頭には、「女だ」という意識がなかった。
小学校にあがれば、兄もその友人もサッカークラブに入った。私は1人になって、サッカー "みたいな" 遊びをした。友達が出来始めると、サッカー "みたいなもの" を教えた。低学年までは、男子も一緒に遊んでいただろう。
けれどクラブが始まると、男子と一緒にサッカーするなんてことはありえなかった。彼らはクラブで指導を受けた。私は原っぱでボールを無駄に蹴っていた。クラブで指導を受けた彼らは足についてる筋肉も違った。走り方も、ボールの奪い方もまるで違った。ルールがそこには存在し、勝つべき相手もそこにあり、私はあっという間に居場所をなくし、インドア派になった。
中学になれば、それまで私より小さかった男子は瞬く間に大きくなった。声が低くなった。腕を上げれば脇からモジャモジャと毛がのぞいた。いつだって教室の隅で固まってエッチな話をしていた。
私は、私の意志とはまるで無関係に、ふくらんでゆく乳房と、増える陰毛を、呪うしかなかった。
丁度その頃Jリーグが始まってにわかにサッカーの人気が高まった。女子の間でもサッカーが話題になった。私は試合中継を見て、「あそこでロングパスを出したのは失敗だ」と、知識があるっぽい振る舞いをしてみせた。けれどサッカー部の連中や男子のほうが圧倒的に詳しく、それも実演を交えて説明をするので、私はとても置いてけぼりだった。
そういえば琴子だったのか。そんなに好きなら女子サッカーをすれば?と言ったのは。彼女はそうして私に女子サッカーのできる希少な高校のパンフレットを見せた。けれど私は中堅の高校に進学し、中学同様美術部に所属した。ボールを蹴ることは、もうなかった。
「家庭科の授業があるでしょう。サナギさんの頃はどうだったか知らないけれど、僕らは男女共同参画世代で、家庭科も技術科も、男女関係なくする世代だから」
「ダリ」がそんなことを言ったのは、植物園の休憩室であった。私と「ダリ」は出会って以来こうして2人で出かけることが多い。私はいささか年若い彼に擬似恋愛のような感情を抱いていないこともなかったが、彼からすれば私は「女友達」なのだろう。そう思えば自分の中途半端さが情けない。
「私も男女共同参画世代よ、悪いけど」
意地悪を込めて言うと、彼は目の前に飾られた生け花をスケッチしながら失笑。「"切り上げ"で計算してしまった」。つまり24歳は30歳だということか、別に構わないけれど。
「とにかく家庭科の授業でね、小学校の頃、周りの男の子は、"女子みたいなことことやりたくない" なんて言うんだ。僕らは、男らしさだとか女らしさという概念が微妙な世代だからね。でも僕は嬉しかった。料理が好きとか、そういうことではなくて、料理をすれば僕はきちんと女の子になれるような気がした」
たとえばそれが、男子だけを寄せ集めて「男の子も料理をする時代です」なんていう授業だったら、僕はかなわなかっただろうなあ、「ダリ」は美しい百合をスケッチブックに生みつつ言った。
私はその隣で、行きかう人々をスケッチしながら、「敵チームに "今日はこっちに来ていいよ" と言われた感じね」と、先日のファミレスでのお返しをした。その自分の言葉に、何かひっかかるものを覚えたが――
ユキの家に行く日、琴子は疲れた顔で現れた。「ひどいね」と言うと苦笑いし、「今ね、次の部長決めてるのよ」と言った。この表情は、また胃薬の世話になっているのだ。たいした苦労人だ。「決まらないの?」荷物持つよ、と、彼女の手から包みを取ると、私は歩き出した。
「ほぼ決まってるんだけどね。キノくんて男の子。でももう1人の男の子がね、"俺もやってみたい" て言うのよ」
「器じゃないのに?」その台詞はひどくスルリと口から出たけれど。
「そう、器じゃないのに。部長って、少し冷静な判断が必要でしょう。中学生なわけだし。彼のポジションて、そこじゃないの。かきまわして、騒いで、彼も気がつかないうちに盛り上げてしまうっていう――そこなんだけどなあ」
彼のポジションはそこじゃない。
ごくごく普通の言葉に、私の心臓は硬直した。
チームを変えるか、ポジションを変えるか――
フィールドの中で、自分のポジションを守ることができない私が頭に浮かんだ。歩くと振動が体に伝わり、ふくらみすぎた胸を微かに揺らす。「ダリ」は大きく手を振って、「向こう」のチームに行くところだった。