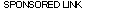西国分寺
いつものように、ここで降りて、待ち構えている階段を上るわけだ。
背中の武蔵野線の喧騒は無視して改札をピッと出て左に曲がる。
またもぎこちない私服の僕は直射日光に似合わない。
そうして落書きだらけの線路下のトンネルを潜る時に、
僕はいつも罪悪感を感じてしまう。
返事を出していないメールが溜っているなんてことはない。
僕はすぐに返事をするし、あなたがくれるメールなんて僅かなものだ。
ただし、僕からメールをすることはそれより遙かに少ないけれど。
「いつでも寄ってくれていいから」
僕らの関係は深くて長かったけれど、不連続だった。
例えるならオルゴールの一周に一度しか鳴らない音を鳴らす
突起みたいなものだった。
不連続にしているのは僕のほうだった。
本当は興味がないのだろうと思う。
でもオルゴールをとめることはできなかった。
トンネルを抜けるとまた日光が僕の頭に注ぐ。
でも少し気が晴れる。
このトンネルは西国分寺への僕のイメージの象徴だ。
西国分寺を想うときにこのトンネルを想う。
そしてそれだけで罪悪感を感じる。
僕とあなたをつなぐのがこの場所だから、
あなたを想うときに西国分寺を想う。
そしてそれだけで罪悪感を感じる。
僕の罪悪感は不連続のせいじゃない、それは許されている。
でもオルゴールをとめられないのは、それが義務だからだ。
不連続でも、こうして、あなたのところへ足を運ぶことが。
歩く距離は少しだけなのに、じわりと体が汗ばんでくる。
残暑とこの日光のせいだろうと思う。
そう思いたい。
僕の罪悪感の正体を、
いつあなたに見破られるのか怖くて、
冷や汗をかいているなんて、
思いたくはない。
高層マンションの団地、その中の一棟へ。
ずっと日陰のタイル張りのロビーは肌寒いくらいに涼しい。
自動ドアの前のパネルで、あなたの部屋の番号を押す。
ややあって「待ってたわ」とあなたの声が聞こえた。
自動ドアが開かれる。
あなたはまだ立って、インターフォンのところまで歩けるんだ。
ふとそんな考えが頭をよぎった。
即座に罪悪感が僕の後頭部を叩く。
エレベーターに乗り、あなたの部屋のある階まではすぐだ。
エレベーターを降りてすぐそこに、
あなたはもう僕を出迎えに待っていた。
「わざわざよく来てくれましたね」
そう言って、あなたは僕を抱き締めた。いつものように。
僕も何か言いながら、あなたを抱き締め返した。
頭の中は罪悪感で占有されているわけでは決してない──
僕はあなたとのひとときを楽しみ、喜んでいる。
罪悪感が居座るのはほんの片隅。
ただ問いかける。
あと何年だろう。もしかしたら何十年だろう。
僕が生きているあいだに、オルゴールはとまってしまう。
そうしたら僕はこの場所に来なくなる。
そしてきっと、もっと足を運べばよかったって後悔するんだ。
もともとそう頻繁に訪れるわけでもなかったくせに。
そんな未来の自分の姿を知っているくせに、
あなたに会いに行かない自分を、責めてくれる。
その姿をあのトンネルに変えて。
あなたを思い出す度に、その後も忘れないように。
いつものようにあなたは僕を部屋に招き入れた。
僕はトンネルをドアの外に残したままそれに従った。