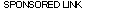小岩
定期券をスーツの内ポケットに押し込み、僕は小岩駅の階段を下りる。
鼻歌でスピッツを歌いながら、桃色に染まった狭い東京の空を見上げると、いつかの日々を思い出す。
恋にも似た、淡い日々を。
僕は中学校から、不登校を繰り返していた。いわゆる「ひきこもり」。
途方もなく長い年月をかけて、部屋から抜け出すことは出来たけれども、まだうまく社会とコミット出来ていない。
そのもどかしさと息苦しさから僕を救い出してくれるのはいつも音楽だった。
部屋から出るときにはいつも、ヘッドフォンから音楽が、血液と一緒に僕の身体を駆けめぐっていた。
彼女を初めて見たのは、レコード屋のバイト帰りのことだった。
ヘッドフォンを突き抜けて届く歌声。
声の鳴る方を見ると、小岩駅に駅に続く階段の側で、華奢な少女がアコギを片手に中島みゆきを歌っていた。
ギターはヘタクソだったけど、その声は透き通っていて力強く、クソみたいな歓楽街の空気をよく震わせていた。
少女は豊かな歌唱力であらゆる歌を歌いこなしていた。
時にはねじ伏せるように、時には音に全てを委ねるように。
僕はヘッドフォンを外し、その歌唱力と表現力に驚きつつ、ただただ聞き入ってしまった。
突然の、バチンというノイズ。声が止まった。
「お兄さん、弦余ってません?」
ボディから力無く垂れ下がる一弦。ギターには、ラフなタッチで描かれたデイジーの花。
六弦を奏でるには少々心許ないほど華奢な指。
穏やかに波打つ黒髪は、左右の側頭部でまとめられている。
その中央にすえられたその顔は、決して整っては居ないけれども、まるで小動物のように可愛らしい。
「ねえ、お兄さん?弦余ってませんか?」
再びの声で、現実に呼び戻された。
たまたまこの日は弾けもしないギターを背負っていたから、スペアも持っていると思われたのだろう。
弦を、手渡した。
人差し指が、僅かに彼女の手のひらに触れた。
ひんやりとした感触。一寸遅れて、こんな薄汚れた歓楽街では絶対に味わえないであろう、いちごのような匂いが、鼻腔を撫でた。
「ありがとう。お礼にこないだ作ったピック。かわいからあげるよ。もってって」
そういって、彼女はボディと同じデイジーの花が描かれたピックを、僕に手渡した。
それから僕は、毎週のように小さな路上ライブへと足を運んだ。
どうしてかは、わからない。けれども、なぜか毎週のように脚を運んでしまうのだ。
そのうちに顔も覚えられたのだろう、僕らは言葉も交わすようになった。
「あたしがここでやってるのはさあ…」と、帰り支度をしながら彼女が呟いた。
「そういえば、どうして?歌舞伎町やら渋谷のほうがスカウトとか来るだろうしさ。こんなクソみたいなところで演るよりいいんじゃない?」
「そりゃ歌舞伎町とかで演ったほうが、そりゃスカウトの目には留まるかもしれないけど、そうじゃないんだよね。もっとすぐ近くで聞いて欲しいし、届けたい人達がいるからさぁ」
いちごミルクのジュースを飲みながら、そういって彼女が投げた視線先には、家路を急ぐ、たくさんの背広の波が見えた。
いつしか、僕がここへ来る理由は微妙に変わってきたのかもしれない。
少しだけ早くなった鼓動を悟られないようにしながら、僕は聞いてみた。
「僕もギターを練習してるんだ。いつか一緒にやれたらいいね」
彼女はにっこりと笑って、そうだね、と言ってくれた。
駅の方針で、路上ライブが出来なくなることが決まったのは、その翌週の事だった。
彼女が言うには、騒音ということで、駅に苦情が届いたのだという。
僕は駅に抗議をしたけれども、さすがに元国鉄。お役所的な駅員も一定の理解は示してくれたものの、所詮は個人的なものでしかなく、ライブが出来なくなるという事実は、ついに覆らなかった。
僕は憤りを隠さなかったけれども、彼女はこの事実について、随分とあっさりしていた。
別に歌うだけならここじゃなくてもいいし。柏か本八幡にでも行くよ。
僕は彼女が下した決断については、支持することしかできなかった。
最後のライブの日。
今日も彼女はやさしく、戦い疲れた人たちに手をさしのべるように歌う。
彼女が僕を呼ぶ。
僕はギターを持って横に座る。互いの右手には、同じデイジーが描かれたピック。
初めて逢った日と同じ香りが僕を包む。あのときと同じいちごの香りが、何故か僕の胸をかきむしる。
彼女が観客に挨拶をする。
「今日でここでのライブは終わりなんですけど…最後にここで、最初で最後のデュエットを!やってみたいと思います」
立ち止まって聞いていた数人からまばらな拍手が零れる中、彼女が選んだ曲は、スピッツの「チェリー」。
// 君を忘れない 曲がりくねった道を行く //
僕もきっと忘れないだろう。
今夜のライブを、
しゃがんで見上げたサラリーマンのオヤジ達の表情を、
やさしい歌声を、
甘く懐かしい、いちごの香りを、
なにより、君のことを。
ささやかな喜びを つぶれるほど抱きしめて。
この日を境に、彼女は小岩から消えてしまった。
いつか候補に挙げていた「次の場所」にも何度か足を伸ばしたけれども、ついに彼女と逢うことは出来なかった。
桃色の夕焼け空は、穏やかに夜の色を湛えはじめる。
会社からの電話を適当に片づけた後、僕はいつものようにイトーヨーカドー側の自動販売機で、缶コーヒーを選ぶ。
小銭入れをまさぐると、120円と一緒に、デイジーが描かれたピックが出てきた。
口元が緩む。
僕はとうとうFのコードを押さえられないまま就職して忙しくなった。
あの夜、デュエットの後にうまいと誉められた歌も、今は会社のカラオケで歌うぐらいだ。
君はまだ、どこかで歌ってる?
ピックを小銭入れに戻し、たいして美味しくもないコーヒーを流し込む。
明日も早番だ。
空き缶をくずかごに放り込んで家路を急ぐ。