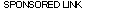イヤな感じのお話
僕が数年前に幕張で出会った男はとても奇妙な男だった。
その男が誰か、僕は未だにわからないでいる。
何処かで逢ったことのあるような気もするし、
全く知らないような気もする、そんな感覚だった。
僕が仕事を辞めてしばらくブラブラしていた数年前。
僕には何もなかった。希望もなく、目標もなく、ただ生きていた。
その当時、僕は幕張に住んでいて休日には多くの人を目にしていたが、
僕に直接関わり合う様な人々は皆無で、その群集は僕にとっては
ただの無機質な塊にしか見えていなかった。
取引先での打ち合わせで人間関係のトラブルを起こした僕は
全人格を否定されるような罵倒を浴びせられながら会社を辞めた。
それまでの多忙極まりない日々と理不尽な人間関係に疲れていた僕は
魂から大事な何かを搾り取られたような気持ちでそこから逃げ出したんだ。
平日でも昼過ぎに起きてひとまず一服するのがその頃の僕の習慣だった。
タバコに手を伸ばすと箱はからっぽで、逆さまにして軽く振ってみると
中からタバコの葉っぱがこぼれてくるだけだった。
僕は仕方なく幕張の駅前にある自動販売機にタバコを買いに行くことにした。
ボロボロのスウェットに白いティーシャツという、いかにもやる気の無さそうな格好で
いつもの自動販売機まで少しうつむきながらトボトボと歩いて行った。
自動販売機の前には異様な雰囲気のある男が立っていた。
その男は真っ黒な帽子を被っていて、コートも真っ黒だった。
真夏の昼過ぎにその姿で立っている男は異様を通り過ぎて異常にも思えた。
僕はしばらく離れたところで立ち止まり、その異常な男を眺めていた。
気味が悪かったからだ。
しばらく待っていれば何処かへ行ってしまうだろうと思ったからだ。
しかし、10分ほど待っても男は自動販売機の前からどく気配が無い。
待ちくたびれた僕は、気味が悪いと思いながらも自動販売機のところまで行くことにした。
少し躊躇いながらゆっくり歩いて行くと、男が静かにこちらを向いた。
男は真っ黒な帽子を深く被ったままで顔は良く見えない。首もこちらには向けていない。
しかし視線だけがこちらを向いているのが何となくわかった。異様な視線。
その視線を感じて僕は再びその場に立ち止まった。
しばらく動けないでいると、男が静かに口を開いた。
『やあ。久しぶりだね。』
男は確かにそう言った。しかし僕はその男を知らない。
いや、顔が見えないからわからないだけなのか。もしかしたら知っている男なのか。
そんなことを考えていると、いつの間にか男が僕の目の前まで移動していた。
鼻先が触れてしまうのではないかというほどの近くに。
そして再び男は言った。
『こんなに久しぶりに逢ったのに遠くから見ているだけだなんてキミも冷たいね。』
やっぱり知っている男なのだろうか。顔を見れば思い出すのだろうか。
しかしこれだけ近くにいるのにもかかわらず男の顔がまだ見えない。
深く被った帽子と真上から照りつける太陽の光に作り出された厚い影が男の顔を隠していた。
僕には男の荒れた唇しか確認できなかった。
しばらく黙っていると、男の唇が歪み少し笑っているように見えた。
そして男はこう言った。
『キミは世界中の不幸を背負っていると思っているのかい?
キミという人間の価値はもうなくなってしまったのかい?』
それを聞いた僕はなんだかとても気分が悪くなった。
そのとき、僕が会社を辞めたときのことが再び頭をよぎった。
取引先の会社に出向いたとき、それまでウマの合わなかったそこの社員と
言い争いになり勢い余った僕はその社員を殴ってしまった。
それまで何ヶ月も欠けて積み上げてきたプロジェクトが全て消えた瞬間だった。
その事件の後、本社に呼ばれた僕はこれ以上無いほどに罵倒され会社を辞める事になった。
僕が勤めていたのは誰もが知っている大手の電気メーカーだった。
当時、エリートである僕の将来を目当てに近づいてきた彼女と結婚の約束をしていたが、
彼女は会社を辞めてしまった僕を捨てて何処かへ消えてしまった。
全てに絶望した僕は実家に戻ることにしたのだが、既に実家にも僕の居場所はなかった。
玄関をくぐると、知らない女がいたのだ。いつの間にか母は家を出ていて父は愛人と再婚していた。
何故僕ばっかりがそんな目にあうんだろう。僕はそう思ったんだ。
理不尽なことばかりの仕事に疲れ、愛する人にも見放され帰るところも無くなって。
嫌なことばかりじゃないか。一生懸命勉強して、エリートコースに乗ったのにロクなことが無い。
どうして僕ばっかり・・・・・・。
そこまで考えたところで男が大声で叫んだ。
『おまえには目が無い!! ワタシと同じように!!!』
そして男は真っ黒な帽子を脱いだ。
男には目がなかった。閉じているのではなく、無いのだ。
さっきは確かに視線を感じたのに、男には目が無かったのだ。
僕はその場にしりもちをついて慌てて後退りをした。
あまりの恐怖に声は出なかった。
周囲を見回すと、平日ということもあり誰もいない。
世界中に僕とこの男しかいないような気がした。
僕は恐怖で目を閉じてその場を動けなくなった。
すると男の気配が消えたような気がしたので
ゆっくりと目を開けるとそこにはもう男の姿はなかった。
あれから数年後の今。僕はもうダメになっていた。
自分の目で見た世界を持たず言われるままに勉強しエリートの道を歩んだはずだった僕は
それまで経験したことの無いあの挫折から立ち直ることが出来ずにいた。
ゴミ捨て場で拾った衣服を着て幕張の駅前をフラフラ歩いていた。
そこにはあの自動販売機があった。数年前にあの男と出会った自動販売機。
僕はその自動販売機の下に腕をいれ、小銭が落ちていないか確かめたが何も無かった。
そのまま自動販売機の前で立ち尽くしていると遠くから僕を見ている男がいる。
ボロボロのスウェットと白いティーシャツを着たやる気の感じられない男。
何か見覚えのある男。
僕はハっとした。今の僕がゴミ捨て場で拾った真っ黒な帽子とコートを着ていたからだ。
そして僕は慌てて自分の顔を触った。風景は見えているのに、僕の顔には目が無くなっていた。
すると遠くで見ていたボロボロのスウェットと白いティーシャツを着た男がゆっくりこちらに歩いてくる。
・・・・・・これじゃ。これじゃまるで・・・・・。
【おしまい】