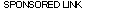夜歩く
夜の雨は嫌いじゃない。
細く濃やかに降る雨は、あらゆる喧騒を包み込んで、穏やかな微睡みに変えてくれる。
雨音だけが、耳に静かに語りかける。
それは、どこか優しい歌に似ていた。
だから、ボクは外に出た。
傘なんかいらない。
必要ない。
飛ぶように軽やかに、舞うように柔らかに、靴先が大地で踊る。
夜はまだまだ長く、雨もまだまだ止みそうにない。
──ひどく、楽しい。
立ち込める雲が星々を覆い、月は遥か高みにありて孤独に遊ぶ。
降りしきる雨の音を聴きながら、ボクは一人、夜歩く。
※ ※ ※
『I'm singin' in the rain ♪
Just singin' in the rain ♪』
古い映画で流れていたオールディズを口ずさみながら、水たまりを跳ね上げる。
……鼻腔をくすぐる、濃厚な水の匂い。
青白く照らす街灯に、銀色の雨がぼんやりと浮かぶ。
深い海の底を歩いている気分だった。
視界は薄く閉ざされて、すれ違う人の顔さえ、はっきりとしない。
雨に煙る街並みは暗く、立体感を失って平坦な影に沈んでいた。
家々から洩れる明かりが、さらなる陰影を刻み込む。
──どこか、夢のような感覚。
ふわふわと、心が一つに定まらない。
夜の雨には、現実感を喪失させるチカラがあるのかもしれない。
見つめる光景は幻燈に照らされた影絵のようで、ボクの姿は影法師となって黒く塗り潰されている。
……光と影だけが入り込める、奇妙な世界。
歩むうちに、どこか知らない異界に迷い込んでしまったような、不思議な不安と期待があった。
過去と未来が逆転して、現実に入り込んでくる。
そんな幻想を抱きながら、ボクは一人、夜を歩く。
狭い路地はうねうねと曲がりくねり、見慣れない道を見つけると、とりあえず入ってみる。
夜の散歩は興味深い。
知らない路地を歩むうちに、意図しないモノを見つけたり、意外な近道を見つけたりと、楽しみは尽きない。
──レンガで築かれた古びた家屋。
──花に囲まれた小さな公園。
──高架下に描き殴られた、思わず見惚れるデザインの落書き。
いつもなら見逃してしまう光景が、びっくりするほど新鮮に目に飛び込んでくる。
それが、ひどく面白い。
建物から洩れる窓の光に、人々の営みを想うのもいい。
生命の息吹が、そこにはある。
暖かな家庭。
醒めた家庭。
安らかな眠りにつくモノ。
〆切に追われて眠れないモノ。
明日、初めてのデートに胸躍らせる少女がいるかもしれない。
混沌とした未来に、苦悩して涙する老人がいるかもしれない。
──そのひとつひとつが、切なくて美しいキラメキを放っている。
それは、生きているからこそ味わえる歓喜であるからだ。
それは、生きているからこそ噛み締める苦痛であるからだ。
……ボクには、それが羨ましい。
正直、妬ましいと言ってもいいだろう。
夜に生きるモノの、太陽への憧憬にも似た想い。
路地を抜けると、ブロック塀の影に身を隠していた黒猫と目が合った。
立ち止まるボクに、黒猫は怪訝そうに首を傾げ、「ニャー」と小さな声で鳴いた。
戸惑うような仕草に、ボクの口許が思わず綻ぶ。
無理もない。
どれだけ猫が勘の鋭い動物だとしても、おそらくボクを理解することはできない。
感じ取ることしか、できまい。
不意に、むくむくと悪戯心が芽生えてきた。
ボクはそうっと黒猫の傍へと近づくと、いきなりその前で手を叩いた。
──パチン。
しかし、夜を震わす音はなく、黒猫は素知らぬ様子で自分の顔を舐めている。
まるで、何事もなかったように。
……その事実が、滑稽だった。
……その事実が、悲しかった。
ボクは皮肉げに口許を歪めると、黒猫に「サヨナラ」と小さく手を振った。
雨が、孤独なボクを覆い隠す。
優しい雨に包まれて、ボクは一人、夜歩く。
※ ※ ※
眩しい光が、夜気を切り裂いた。
……ゴトン、ゴトン。
迫り来る駆動音。
……ゴトン、ゴトン。
近づいてくる。
……ゴトン、ゴトン。
当然、ボクには気づかない。
一輌だけの路面電車が、ボクの鼻先をかすめて通る。
目の前を、窓からこぼれる明かりが照らしつける。
四角く切り取られた窓の向こう、まばらに腰かけた人々の姿が目に飛び込んできた。
──疲れ切って眠る男性。
──虚ろに宙を見つめる老女。
──ひたすらに携帯を手に取る若者。
垣間見た人々の顔は、どれもがのっぺりと無表情で、よくできた人形を思わせた。
人間味に欠けた、同じような、顔、顔、顔……。
なぜか、ゾッとした。
精気に欠けた表情は、死者のそれを思い出させる。
……カタチのない人間。
……明日の見えない人間。
奇妙に歪んだオブジェ。
それは、記憶に埋もれた過去を連想させた。
高揚した気分が消えていくのを、ボクは感じた。
ぼんやりと、周囲を見渡してみる。
ここがどこか、今がいつなのかを、改めて見つめてみる。
大通りの中心に立つボクの隣を、多くの車が轟音を立てて走り去る。
高層ビルが立ち並び、深夜でも多くの店のネオンが狂気のように輝いてる。
……文化的で便利さに満ちた光景。
……短絡的で狡猾さに溢れた時代。
けれど、それは蜃気楼のようにあやふやで、いつ消えてしまってもおかしくはない。
かつて、そんな瞬間を、ボクは見てきた。
──大地を舐める、ホノオのシタ。
──黒ずんで倒れたヒトのカタチ。
赤黒く焼きついた肌は、触れるとプルンと弾けて真っ赤な肉をさらけ出した。
異臭に顔をしかめ、膿だらけの身体をよじる人々。
慟哭と絶叫、静寂と死が満ちあふれた世界。
廃墟と化した街並みは、さながら地獄を彷彿させる光景だった。
いや、地獄ではない。
それは現実に起こったコトだ。
二度と繰り返してはならない悲劇だ。
……ひどい時代があった。
……ひどい戦争があった。
それは、一方的な殺戮以外のナニモノでもなかった。
小さな太陽を、ボクは見た。
けれど、それは太陽なんてモノではなかった。
すべて破壊し犯し奪い去る、ヒトが作り出した真っ黒な意思。
痛かった。
痛いなんてモノではなかった。
苦しかった。
苦しいなんてモノではなかった。
泣きたかった。
だけど、涙する身体はとっくになくなっていて。
誰もが、泣くことなんてできなかった。
……閃光と衝撃、灼熱と爆風。
大勢のヒトが、その時、死んだ。
大勢のヒトが、その後、死んだ。
無差別に、無慈悲に、無関心に、徹底的にボクたちは殺された。
──忘れてはならない。
──忘れて欲しくない。
けれど、時代は変わり、人々の心は過去を失って行く。
未来を見つめるコトもできず、現在を満足するコトもなく、過去を葬り去ろうとする。
時代を生きた語り部たちは姿を消し、やがて一人もいなくなる。
それは、仕方のないコトだけど。
あの時の惨劇を、あの時の狂気を、あの時の絶望を、ボクは忘れて欲しくない。
そして、今──
……ボクたちは、もう一度殺されようとしている。
人々の記憶から消える時、残された想いが忘れ去られる時、ヒトは死ぬ。
──それは新たな殺戮と変わらないのではないだろうか。
改めて、周囲を見渡す。
雨に煙る街並みは暗く、立体感を失って平坦な影に沈んでいる。
家々から洩れる明かりが、さらなる陰影を刻み込む。
それは、いつ消えてもおかしくない幻燈の明かりにも似て、ボクを不安にさせる。
苛立たせる。
立ち尽くすボクの身体を、多くの車がすり抜けていく。
実体のない、空気のような存在のボクを、誰も気づくコトはできない。
雨が降る。
ボクの身体を貫いて、雨が降る。
雨に霞む世界は影絵のようで、虚しさに心が狂い出しそうになる。
……たまらない気分だった。
……叫び出したい気分だった。
ふわふわと心が一つに定まらない。
──ひどく、悲しい。
夜が、ボクをそっと抱きしめる。
雨が降っている。
静かに雨が降っている。
傘なんかいらない。
必要ない。
ボクは、ただ夜に生きる過去の残滓にすぎないのだから。
優しい雨に包まれてボクは一人、夜歩く。
※ ※ ※
夜の道を歩いていく。
夜の雨を渡っていく。
ボクに気がつくモノはなく、孤独さは募り、絶望が全身を支配する。
いくつか橋を渡り、川に沿って夜を歩く。
視界の片隅に、特徴のある建物が映った。
無残な残骸を晒しながら、無言で夜に立ち尽くしている。
雨に打たれる影は醜く、けれど、消えるコトすら許されない。
その姿に、ボクは自分と同じ悲劇を見た。
……心が、震える。
正視するコトができす、ボクはただ川岸に沿って夜を歩いた。
逃げるように。
忘れるように。
どれほど歩いたのだろう。
ふと見ると、流れる川の中に、おかしなモノが引っかかっていた。
妙に、心に訴える。
川岸をり、改めて近づいて、それは解れて壊れた灯籠だった。
大勢の人々がつめかけ、さながらお祭りのように繰り返される行事を思い出す。
……戦没者の慰霊のために、毎年夏になると流される、色とりどりの灯籠の群れ。
……ゆらゆらと陽炎のように流れていく、過去への慙愧。
夕暮れを背に、水面に浮かんで流れる灯籠の炎は、美しく切なく、限りなく悲しい。
どうやら、その時に流した灯籠の一部が回収されずに残されていたらしい。
過ぎ去った過去への想いを託す、意味のある行事。
──しかし、いつかは形骸化し、消えてしまうかもしれない。
──それは、遠くない未来なのかもしれない。
不安と絶望が、ボクを苛む。
苦悩しながら、壊れた灯籠を取り上げると、ぼんやりとそれを見た。
奇跡的に張りついたままの紙には、たどたどしい字で何か書かれていた。
けれど、完全に破れていて、字の判別などできない。
過去を垣間見ることなど、ボクに取っては造作もない。
そっと撫でることで、ボクは灯籠の過去を取り出した。
ボロボロの灯籠は一瞬で姿を変え、流される前の状態でボクの腕の中に生まれ変わった。
年端のいかない子供が書いたのだろう、クレヨンで書かれた文字は読みづらかった。
だけど、はっきりとそれは読み取れた。
……衝撃が、ボクの心を走り抜けた。
『せかいがへいわでありますように』
それは、純粋な平和への祈り──
ささやかでちっぽけな、けれど大切な願いを込めて。
──限りない未来へのメッセージ。
自然と、ボクの顔に笑みが浮かんだ。
どれほど絶望があろうとも、どれほど困難があろうとも。
……変わらない想いが、ココにあった。
それは、誰もが望む無意識の祈りに他ならない。
子供たちは純粋だ。
その純粋さで、明日の平和を願っている。
託されたバトンは、時代を越えても、カタチを変えても、途切れることなく渡されていく。
受け継がれる。
現実を生きた語り部たちは、いずれ消える。
それは、仕方のないコトだけど。
あの時の惨劇を、あの時の狂気を、あの時の絶望を、忘れて欲しくない。
そして、未来──
伝える意思は、魂に刻まれて受け継がれる。
……それは、祈りという名の希望。
たまらなく嬉しい気分だった。
たまらなく泣きたい気分だった。
ボクは手にした灯篭に火をつけると、雨降る夜にそっと流してやった。
濃やかに立ち込める闇の中に、小さな小さな炎が揺れる。
ささやかな満足感。
それだけで、充分だった。
──その、瞬間。
おびただしい色彩が、川面を染めた。
青、赤、黄、白、緑──見るも鮮やかな灯籠が、視界を埋め尽くさんばかりに流れてくる。
……ゆらゆらと揺れる炎。
……人々の願う、祈りのカタチ。
もちろん、それは現実の灯籠ではない。
戦没者を慰霊し、二度と同じ悲劇を繰り返してはならないと、心から願って流された想い。
世界が、それを覚えている。
世界が、その幻想を見せる。
祈りはカタチとなり、灯籠となってどこまでもどこまでも流れていく。
灯された炎は儚く、けれど果てしなく強く永遠に燃え続ける。
──ボクは、それを夢見た。
──ボクは、それを信じた。
どれほどの時間が経ったのだろう。
満ち足りた気分で、ボクは静かに空を仰ぎ見た。
いつしか雨は消え、かすかな陽光が東の空を赤く染める。
……もう、夜は終わりを迎える。
……ボクの時間も今日は終わる。
立ち昇る朝日に、ゆっくりと消えていく自分を感じながら、ボクの心は爽やかに透明だった。
ひどく、満ち足りた気分だ。
日は昇り沈み、やがて夜が訪れる。
優しさに包まれて、今夜も僕は一人、夜歩く──