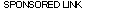月夜話
ある月の夜、漁に出ようと浜辺に出ると、見たことのない1人の男が立っていた。
僕は銛を背中に隠して、そっと彼に近づいた。山と森に囲まれたこの小さな集落に入ってくる外部の人間はそうそういない。いるとすれば、それは物盗りだとか、いくさを好むクニの者たちだ。とにかく、真っ当な者であるはずがなかった。
かなり警戒して、足音はなるべく立てなかったつもりだったけれど、彼は僕に気がついた。
「やあ」
その人は、漆黒の髪と漆黒の綺麗な服を着ていた。その優しそうな表情に、僕は少しの間見惚れた。
彼は服の中から袋を取り出すと、紐をほどき、その中味を海に流した。
袋の中からは赤い砂が出てきて、月に照らされた海の上に人型のような赤い影を作った。
僕は驚き、恐怖心を抱きながらも、背に隠していた銛を取り出し、男のあごに向けた。
「何をした!」
漆黒の服、漆黒の髪。そして、山に閉ざされたこの海岸にやってきたという奇妙さ。この男、おそらく悪い呪術を使う、化け物だ。
銛を握る僕の手はじっとりと汗をかいた。長いことそうしていた。
けれど、彼は微笑んだままだった。
僕の恐怖心と驚きは、その笑顔に魅せられてやがて消えていった。
僕は砂浜にぺたりと腰を下ろした。
漁をする気が失せた。
僕が月夜に漁に出るのには理由があった。
僕みたいな子どもが漁をするのを大人は嫌がる。却って獲物が逃げてゆくからだと。
それでも、多くの子どもがそうするように僕は小さい頃からずっと毎日父さんと一緒に漁をしていた。
母さんは僕が覚えていないくらいずっと前に死んでしまったから、僕と父さんは、裏に住んでるばあさんにお節介を受けながら2人で暮らしてきた。
それが、ある日ぱったりと、父さんは僕を漁に連れて行かなくなった。
父さんは僕を避け、「漁はしばらく父さん1人で行く」と言っては遅くまで帰らなかった。
夕御飯を僕はひとりで食べて、父さんが帰ってくると、父さんは僕に「月の明るいうちに漁の練習に行け」と言った。
月のない夜は、父さんは「見回りをしてくる」と言っては僕と寝ることを拒んだ。
父さんはたまに変な咳をしては僕に背を向けた。漁に出る僕と帰ってきた父さんがすれ違う時、以前に増して父さんの顔色は悪くなっていた。
人が死んでしまう時には何となくわかるもんだ、と、ばあさんは言っていた。
僕は、何となく感じていた。
隣に立ったままの男は、海に、もうひとつ砂を流した。赤い砂。人型になって、流れて、やがて海に溶けていく。
男は僕の隣にしゃがみこむと、海の方向を指した。
「綺麗だろう?」
月はますます輝いた。おかしなことに、この男のそばにいると、やけに月が近くに見える。
「愛する者が悲しい死に方をした時にはね、美しく弔ってやらなくちゃいけないんだ」
男は目を細めて海の遠くを見た。
パシャン、と、遠くで一匹、魚が跳ねた。一番高く飛んだ瞬間、月に照らされて魚は金色に輝いた。
そして、魚が海にポチャン、と音を立てて戻るのと入れ替わりに、1人の女の人の姿が、海の上に浮かび上がった。
とてもきれいな、背筋のしゃんとした女の人だった。
その人は、男のほうを向くと、にこりと笑い、少しずつ透明になりながら、空へと昇っていった。
男の人も、にっこり笑った。
その後、もう一度魚が跳ねた。
次に現れたのは、僕と同じくらいの年に見える女の子だった。その子は、笑うんじゃなくって、泣いていた。
男は、
「空の上なら、いつでも、誰にでも会える」
と、囁くように言った。
僕にしか聞こえないような小さな声だったけれど、その声は女の子に届いたのだろうか。女の子は愛らしい笑顔を作って、それでも涙を流したまま、ゆっくり透明になって、空に昇った。
女の子の流した涙だけが、ぽつん、ぽつん、と、海に落ちた。男が手を伸ばすと、その涙のひと粒が、すっと彼の手に引き寄せられた。
男は、その涙の粒を手で握った。そして、次に手を開いたとき、彼の手のひらにあったのは、丸くて透明な美しい石だった。
僕はそれを見ると、銛を手放して、頭を深く下げて跪いていた。
この人は化け物なんかじゃない。
きっと神様だ。
僕は、神様を銛で突こうとしていたのだ。
そう思うと畏れ多く、砂に顔が埋もれるほどに頭を下げないわけにはいかなかった。
その頭に、やさしく触れるものがあった。
僕は頭を少し上げた。
僕の頭に触れているのは、神様の手のひらだった。
神様のからだは、白く、昼間の月のようにぼんやり光を放っていた。
瞬間、僕の頭の中に珊瑚が産卵する様子が広がった。
海の中に潜り込んだかと錯覚するほどだった。
見覚えがある景色。
数年前の満月の夜、父さんと2人で海に潜ったときの景色だ。
「しっかり見ないと暗くて見えないぞ」
と、ずいぶん近づいて見たのだった。
幻想的な珊瑚の産卵を僕は海水に痛む目をしっかり見開いてみた。
月明かりがちらり、ちらりと幾千という小さなあぶくのような卵を照らした。
海から上がると、僕と父さんは砂浜から海に映る満月を見た。
父さんは笑顔で言った。
「綺麗だっただろう。いのちっていうのは、ああいうものなんだ」
ふ、と、記憶から意識を戻して気がつけば、隣にいたはずの神様がいなくなっていた。
代わりに、僕の手のひらの中に、先ほどの丸い透明な石があった。
突然僕は、確信した。
そして、砂浜を走って戻った。
僕が家に近づくと、既に裏のばあさんが家の前に立っていた。
「予感がしとったんだ」
ばあさんはそう言って、僕を家に入れた。
そこには、生きた匂いはなかった。頭の中で、魚が一匹、ポチャリ、と跳ねた。
「明日の朝にでも、流してやろうぞ。今夜は巫女を呼んで、悪いモノが憑かんようにしてもらわんと」
ばあさんはそう言って、曲がった腰でヤシロに向かった。
僕は、静かになった父さんに近寄った。
苦しそうな顔をしていた。
そっと、父さんの冷たくなった唇を開き、神様から頂いた石をその中に入れた。
石は、父さんの口で、涙のように溶けて流れていった。
父さんの顔が少し優しくなったように見えた。
次の日、太陽が昇ると、巫女様が父さんの遺体と僕に何かを呟きかけた。悪いモノが家に寄らないための呪文らしかった。
漁の仲間が父さんの体をかついで、海に流した。
太陽の光は父さんの体が流れていく姿を、照らし続けていた。
父さんの姿が見えなくなっても。
太陽は父さんが流れた跡をキラキラ照らし続けた。