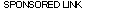神代奇譚 ~カミシロキタン~
神代奇譚
~カミシロキタン~
1.スズメ
深く繁った森の奥から、足音を立てることもなく、風が立てる木々のざわめきだけにリズムを合わせ、それこそ風のようにスズメは飛び出してきた。森を抜けると木々がまばらになり、集落が見える。
(早く知らせなくては)
その思いだけでスズメは集落の中心部――お宮――の入り口に走りたった。
お宮の番人はスズメの切羽詰った表情を見て事態を悟る。
番人がスズメとともにお宮の入り口からボソボソと合言葉を告げる。お宮の扉が開けられると、中心に置かれた松明の明かりだけがぼうやりと、数人の巫女と、1人の女を照らした。
女は言葉を発することもなく、視線だけでスズメを中に入れた。番人は出て行く。
スズメは深く礼をしてから、呼吸を整えると、凛とした声で報告を行った。
「ヤマタのクニは呪術ならぬ、光る槍や弓、刀剣を持っております。わたくしが調べに入った日にはトドロのクニへいくさをしかける話し合いを行っておりました。その後トドロのクニを見ましたところ、トドロのクニでもいくさの準備を始めておりました。しかしヤマタのクニの武具に比べましたらトドロのクニの武具は見苦しいもの。ヤマタのクニが東へ進出し、やがて我がタカマのクニにまでやってくるのは時間の問題かと思われます。取り急ぎ、対策を練られたほうがよろしいかと思います」
そこまで一気に報告すると、巫女が1人、お宮の端においてある瓶から器に水を汲み、水の中に唾を吐いた。続いて隣に控えた巫女が唾を吐き、最後の巫女が唾を吐くと、スズメの頭に水をかけた。他のクニへ行って来た者を浄化する簡易な儀式である。
スズメは深々と頭を下げると、女の視線に従ってお宮の扉の前で再び合言葉を告げた。扉は開かれ、再び眩しい太陽の下に出る。
番人は「ご苦労だった」とスズメにひとこと告げる。スズメは頭を下げてお宮を離れると、また走り出し、森に向かった。森の手前にある岩を動かすと、その下の洞窟がスズメの住む場所である。
やはり足音を立てず、細い階段を下っていく。光は失われた。通常、突然の明かりの変化に人の目が順応するのは遅いが、スズメは違った。どのような場所でも、どこにいても「景色」を見ることが出来た。
「おかえり」
地下洞内に響く囁きのような声がスズメを迎え入れた。
「ツクヨミ様」
声の主はすらりと背の高い、漆黒の髪と漆黒の服を着た男である。男はスズメを抱きしめると、つむじに唇を当てた。
「だいぶ疲れているようだね」
その声にスズメは首を横に振ったが、ふと気を抜いた隙に足元がぐらついた。5日間走り続けたのだ。ツクヨミは腰をかがめてスズメの足に手を添えた。ツクヨミの手から白い光が出て、スズメの足を撫でた。
「少しは楽になっただろう」
スズメは、コクン、と、うなずいて、跪き、「ありがとうございます」と礼をした。それから、自分の修行所である洞内の横穴に入り、横になった。
向かいの横穴にいるサキが、スズメの穴にやってきて、いくつかの果実を渡した。
「ありがとう」
果実をひとつ、かじると、甘味と水分が体中に広がった。この5日間を癒すようだ。
サキも、ひとつ果実を手に取り、かじった。そして、スズメの手に触れ
「危ないのね」
と、ひとこと述べた。
スズメは横になったまま「どんな先が見える?」と問うた。
サキは「あんたの危惧そのままよ」と答えた。
そのやり取りを聞いていたキキトリが「オムナ様は武具を増やすことを考えていないようだ」と呟いた。
「むやみにオムナの声を聞くんじゃないよ」
ツクヨミはキキトリに厳しく囁いた。キキトリはサキとスズメにチラリと舌を見せると、修行を再開した。瞳を閉じて、体の穴という穴から体の中に入り込んでくる声に、あるものには注意を傾け、あるものは聞かないようにする。そのコントロールがこの少年には必要であった。
ツクヨミが管理するこの洞内ではときとしてうめき声が聞こえた。ここは、特殊な能力を持った者たちが集められ、その力を高めるための場である。彼らの力は制御が出来ないほどに大きいがために、ツクヨミがこの洞内を修行地に選ぶ前には、大きな騒ぎを起こし、集落の人々に不安を与えることが多かったという。うめく声はコントロールに苦しむ声である。
スズメはどこにいても全てのものが見えてしまう。気を抜けばこの洞窟の外の地上にある太陽どころか遠く離れた土地での出来事でさえ見えてしまう。全てを見ないで、見たいものだけを見るようにすることが、少女の精神の安定には必要だった。それでも、見たくないものが見えてしまうときも、見なければならないときもある。
そしてサキは、人に触れることで、その人物の記憶が紡ぎ出す先を読むことが出来た。この能力は非常に重宝されており、洞内にいる者の中でもサキはもっともお宮に呼ばれることが多かった。
そして今回も、
「サキ、オムナ様が呼んでいる。スズメとネムリを連れてお宮に来るように、と」
キキトリが告げた。
2.オムナ様
ネムリが目覚めたときには、すでにお宮の中にいた。
全ての巫女が出払い、女―――オムナ様、サキ、スズメ、ネムリの4人だけがそこにいた。
オムナが口を開く。
「ネムリ、どのような夢を見た」
ネムリは洞内にいる能力者たちの中では最も幼い。まだ言葉すらきちんと使うことすらできないような幼女である。しかし、その幼さ故か、サキが読んだ先の未来を捻じ曲げるための夢を見るという能力を持っていた。
ネムリはまだぼんやりしながら、夢の内容を少しずつ話し始めた。
「キラキラしてるものが、人を殺せる。キラキラしてるものは、海の向こうにたくさんある。キラキラがないと、死んじゃう」
オムナは次にスズメに問う。
「光る武具は、海を渡らねば手に入らぬか。ここらで作ることは出来ぬか」
「光る武具は、特別な加工を施されているようです。材料は見えますが、加工方法は見えません」
オムナは次にサキに問う。
「ネムリの先を読め」
「降伏か、全壊のどちらかです」
「降伏のときはどうなる」
「失礼申し上げます。オムナ様が、殺されます」
「全壊のときはどうなる」
「失礼申し上げます。ヤマタの軍も、タカマの民も、我々異端者の能力制御が効かなくなることで、全滅いたします。無論、我々も」
「タカマが勝つ先は見えぬのか」
「失礼申し上げます。今の私には、見えませぬ」
オムナはさらにネムリに問う。
「死なない夢は見なかったか」
「見た」
オムナの瞳孔が大きく開いた。
「それはどのような夢だった?」
するとネムリは、夢の内容を思い出したのか、わんわん泣き始め、何も言わなかった。サキがその手に触れようとするより前に、オムナは立ち上がり、瞳を閉じてネムリの頭に唇を当てた。
しばらくの時間、オムナはそうしていた。ネムリは母親に甘えるようにオムナにしがみついて泣き続け、やがて泣き疲れて眠った。
フと、オムナの睫毛を濡らして涙が流れた。サキとスズメは驚いた。決して感情を顕わにすることのないオムナであった。驚きを隠そうと、スズメはサキの手をつないだ。そうするだけで二人は会話が出来た。
(オムナ様はどんな先を見ているの?)
(まったくわからない)
(スズメ、次はどんな夢を見るのかな)
(そこまでわかるのはツクヨミ様くらいだよ)
(あ、ツクヨミ様がいらっしゃってる)
(え?)
(お宮に向かって来てる)
オムナはネムリの頭から唇を離した一瞬、涙を流しながらお宮の外の太陽を見上げて微笑んだ。そして、いつもの硬い表情になると、
「ネムリを連れて、戻りなさい」
と、丁寧に自分の腕の中のネムリをサキに抱かせた。ネムリはそれでも眠り続けていた。
サキとスズメがお宮を出るのとすれ違うようにして、ツクヨミがやってきた。
「ほら」
スズメはサキに囁いて、ツクヨミに頭を下げた。ツクヨミは柔らかく微笑し、2人を見送った。
しばらく歩いてから、サキがスズメに「ツクヨミ様が好きなんでしょう?」と、言った。
スズメは驚いたが、「それは、親切にしてくれる方だから」と、顔を赤くして答えた。
サキは「スズメも女らしいところがあるんだね」と、意地悪そうに笑い、ネムリを抱きながら肘でスズメの小さな胸をつつき「ああ、ここがもう少し大きければねえ」と、からかった。
スズメは顔を赤くしたまま口をつぐんで、何も言わなくなった。
遠くの物まで見通せる少女は、幼い頃から偵察用に鍛えられてきた。サキやキキトリがほとんど集落を出ないのとは正反対に、スズメは遠くまで偵察に出るため並外れた体力を持っていた。それ故に、年のほとんど変わらないサキとも胸の膨らみは全く違った。
そのスズメの声には出さない言葉を、それは特異な能力ではなく、人として当然の能力で、サキは読み取り、呟いた。
「大丈夫。スズメは、最期までツクヨミ様と一緒だよ」
3.森
その日、スズメは前回よりもずっと鬼気迫った表情で森を駆け抜けていた。途中、鹿のオサがいる山深いところまで足を運んだ。他の獣たちにも知らせるべきだと感じたが、それだけの時間はなかった。この森の獣のオサは鹿のオサである。小さな川に沿って急いた。森を進むにつれて獣道すら見えなくなる。自分の足跡を残さぬよう、スズメは木の幹から木の幹へと足を運ばせた。
やがて、川は細くなり湧水のそばまで来た。オサが住んでいるのはそれよりさらに奥である。
森の一番深く、そして一番高い位置に、巨木がある。巨木の根のひとつの周囲にぽっかりと空洞がある。スズメはその根につかまり、空洞へと降りた。降りてゆくにつれて温度が下がり、ひやりとした風を感じた。しかしまたも5日間走り続けたスズメにはそれが少し心地よかった。
様々な樹木や草花の根が天井にあり、土から浸み込んだ雨水がひとつの池を作っている。池の中央には苔むした巨大な岩がある。その岩の中央に、うっすら白く光る大きな鹿が座していた。オサである。そのオサを守るように、数匹の鹿が耳を立てて立っていた。
「突然の来訪、失礼いたします、オサ」
スズメは深く頭を下げた。オサも護衛も何も言わない。彼らの言葉を聞き取れるのはキキトリとツクヨミだけである。
「西の方角にて、巨大な獣を見ました。今、わたくしの目に見えますのは、ヤマタの民がそれらの獣に乗り、鋭い武具でトドロのクニへと出撃する景色であります。これまでこの森は複雑さと高低の激しさから西のクニから攻め入られることはありませんでした。わたくしどものクニはこの森に守られ続けておりました。しかし、今、ヤマタの軍があの巨大な四肢の獣に乗り、光る武具を手にトドロのクニに続く山を越えております」
スズメは西を必死に見た。
惨殺される獣。なぎ倒される木々。トドロのクニを守る山のオサと、ヤマタの軍の攻防戦。
見たくないもの。しかし今はしっかり神経を研ぎ澄まし、そう遠くはないヤマタの軍の侵入に備えて報告すべきことがある。
「オサ、どうぞこの森の獣たちにお伝えください。静かに隠れるようにお伝えください。そうでなければ、この森の獣たちは殺されてしまいます。今もわたくしの頭には見えております。巨大な獣は山道に強く、光る武具は鋭く獣を斬り殺します。オサ、どうぞこの森のためにも、お隠れくださるようお願いいたします。わたくしどものクニは先日の先読みによりまして、救われないことがわかっております。けれどこの森はお守りください。この森が破れては、この土地が枯れることになるでしょう。どうか、お願いいたします」
急いでおりますので、これにて失礼させていただきます。そう告げて頭をまた深く下げると、スズメは降りてきた根をつかむとすばやく上がっていった。
足音を立てないように足跡を残さないように森を抜けて、お宮に急ぐ。
4.儀式
お宮にスズメが入ってきた途端、オムナは報告も聞かずに「浄化を」と、巫女たちに告げた。今度は水ではなく酒を汲み取り、巫女たちではなくオムナ自身が唾を吐き、何ごとか唱える。スズメを松明の前に立たせ、炎の上に頭をたれさせると、自らの手でスズメに酒をかける。一瞬ゴウッと音を立てて激しく火が燃えたが、すぐにおさまり、そして、スズメには火傷の痕すら見当たらなかった。
「よほど酷い景色を見たな」
浄化の儀式によって落ち着きを取り戻したスズメは、一連の景色の報告を行った。
謎の獣。光る武具。壊される森。
「今も見えております。ヤマタがトドロのクニに突入しました。トドロのオサが出て来ております。いくさにはまだ発展しそうにありません」
若い巫女の1人が瓶から水を汲み、唾を吐いてスズメに渡した。スズメはそれをありがたく飲む。
オムナは、すでに控えさせていたサキにスズメの頭を触らせた。
「いつ頃ヤマタはここに来るか」
「あと2日もすれば来るでしょう。今日のうちにトドロとヤマタはいくさを始めます。しかしヤマタは瞬時にトドロを征服します。トドロで一日休息を取り、明日、わたくしどもタカマのクニを目指します。トドロからあの森を抜けてやってきます。その途中で一旦休息を取り、さらに翌日太陽が昇るとまた動き始めます。昼頃には、お宮の前に着くことでしょう」
「ネムリはどうしている」
「ここ7日間、眠り続けております」
オムナはそれ以上何も言わず、さきほどの若い巫女がサキにも水を飲ませた。
2人が出て行くのを見計らうと、オムナはサキとスズメに水を与えた若い巫女だけを残して他の巫女を出払わせる。
そして、つむじに唇を当てた。続いて瓶から酒を汲み取り、口に含み数回噛んでから、酒を若い巫女に口移しする。若い巫女はそれをやはり数回噛むと、飲み込む。続いて巫女の衣服を脱がせると唾を吐いた酒を全身に浴びさせる。若い巫女は何ごとか言葉を唱え続けた。オムナはさらに松明を手にとり言葉を唱え続けながら巫女の全身に炎を浴びせた。やはり巫女は火傷ひとつない。オムナはまた酒を全身に浴びさせ、衣服の中に隠していた銅刀を松明で焼き、巫女の背中に傷口を作り紋様を描く。傷口からは血が少し滴った。最期に紋様を唾を含んだ舌で全て舐め、水を浴びさせると、再び衣服を着せた。
「オムナ様」
若い巫女は細い声で呟く。
オムナは眉ひとつ動かさずに
「ツクヨミの洞に行け」
と告げた。
若い巫女は涙を流す。オムナは表情ひとつ変えない。
若い巫女は涙を指でそっとふき、お宮を出て行った。
5.異端者たち
洞の岩戸はしっかり閉ざされた。
それぞれの修行場である横穴から能力者たちはツクヨミを中心に円を描くようにして集まった。ツクヨミの隣には、あの、若い巫女がいた。
「突き当たりの土を崩すと縦穴がある。見えるな?スズメ」
「はい」
「その縦穴を降りてゆくと水脈に沿った横穴がある。横穴を進んでゆけば新たに神聖な土地に出る。私もいずれはそこに向かう。そこで再び修行を繰り返せ。お前たち能力者は異端者だ。修行をしなければ普通の生活が営めない。しかし、この大いなる、水と森と大地の世界にはお前たちのような存在が必要なのだ」
ツクヨミはそこまで言うと、突き当りまで進み、手を当てた。手から白い光が出ると、土は崩れて縦穴が現れた。
「アカル」
アカルと呼ばれた少年が立ち上がる。瞳が金色をしている。
「お前が先頭になり、道を照らせ」
アカルの能力は、瞳が光を発することであった。幼い頃はコントロールも効かず、生みの親にも気味悪がられ、この洞内へと連れてこられた。
続いて、ツクヨミは水の匂いを嗅ぎ分ける能力を持つ「ハナ」という老人を指名した。この老人はまだ若い頃に自らの能力に気がつき、能力を高めるために自らツクヨミのもとにやってきた。
「お前は分かれ道で良い水脈を選び、方向をアカルに伝えよ」
そのようにして、幾人かの能力者が役目を指定された。そして
「サキ。お前はネムリと、オムナを守るのだ」
「ネムリと、オムナ様を?」
ツクヨミは頷いた。そして若い巫女を前に出した。
「この女が新たなオムナとなる」
ざわめきが起きる。
「今のオムナ様はどうなる」「死んだのか」「まだ死んでない」「では死ぬのか」
ツクヨミは何も語らなかった。やがてざわめきが自然におさまると、名前を呼ばれなかった者たちと、名前を呼ばれた者たちに分けた。スズメの名は、呼ばれなかった。
「今、名前を呼ばれなかった者たちは、ここに残り、ヤマタのクニとの戦いに協力することになる」
洞内は静まり返った。
ツクヨミは、普段は見せないような厳しい表情で話を続ける。
「アカル。もう行きなさい。時間がない」
「サキ。くれぐれも、オムナとネムリを守るように」
トビハネという男がアカルを抱いてまず縦穴に飛び降りた。この男は驚異的な跳躍力を持っていた。縦穴は深く普通に降りることは不可能である。アカルは瞳を見開いて道を照らした。トビハネは1人ずつ、軽い者は2人両脇に抱えて道行く者たちを縦穴の底に運んだ。
若いオムナとネムリも運び出され、残るはサキとなった。
「トビハネ、ちょっとだけ待ってくれる?」
「ああ、だが急げ」
サキは、スズメに近寄ると、強く抱きしめた。スゥッと、涙が頬を伝った。
スズメも、少し泣いた。
サキは、全ての残された者たちの手に触れていき、背中だけを見せて、何も言わずにトビハネとともに縦穴に消えていった。
ツクヨミが再び、縦穴のあったところに手を触れると、そこはまた突き当たりとなった。
残された者は、スズメ、キキトリ、コエ。コエはやや年のいった女だったが、コントロールがよく効いた。その能力は、自分の声を特定の人物にだけ伝えることであった。
ツクヨミは、残された3人の中央に立って、指示を与えた。サキはヤマタの動きを見てそれをコエに伝える。コエはそれをお宮にいるオムナに伝える。キキトリはオムナの言葉を聞き取り、ツクヨミに伝える。
「サキ、ヤマタは今どこにいる」
「今、トドロを出たところです」
ふむ、と、ツクヨミは瞳を閉じると、3人のつむじに唇を当て、「すぐ帰る。決してその場を動くんじゃない」とだけ言い残し、ふっと消えた。
しばらく沈黙が続いたが、キキトリの泣き声が聞こえ始めた。
「サキの声が、聞こえたんだ」
スズメは、長年一緒にいた同じ年頃の友と離れた寂しさと、次にキキトリが言う言葉を予感し、声に出さずに涙を流した。
「死ぬんだ」
6.ツクヨミ
馬に乗ったヤマタの軍がタカマのクニに続く森の手前に、ツクヨミは立っていた。
「私の声が聞こえる者はいるか」
いつもより大きく出されたツクヨミの声に反応する者は、1人としてヤマタの軍にはいなかった。
ヤマタの軍が森の中に入っていく。大きな馬の蹄は草花を蹴り散らす。
ツクヨミは次に森のオサのところへ行った。
「獣たちは、静かにしているか」
オサの言葉はツクヨミの頭に響いてきた。
「静かにしているようにと伝えた。どのような驚くことがあろうと隠れているようにと。しかし全てのものの命は保障できない。臆病なものもいる」
ツクヨミはオサのいる岩場に立ち入り、オサの2本の角に唇を当てた。そしてしゃがみこむと、次はオサがツクヨミの頭を舐めた。
「ヤマタのクニの人々は、世界のとらえ方がわたしたちとは異なっているようだ。わたしは戦いに参入できない」
それだけ言い残すと、ツクヨミは再び洞内に戻った。
そこにはひととおり涙を流し終えた3人の能力者がいた。ツクヨミは3人の頭に手をかざした。ツクヨミの手のひらから出る光はやわらかく、やさしく、3人は平常心を取り戻した。
ツクヨミは、再び厳しい表情に戻った。
「始める」
7.旅路
アカルを先頭にして、何人もの能力者が地下を歩いていた。ネムリを抱いたサキと、若きオムナを真ん中に挟み、最後尾にはノコラズという女がいた。ノコラズの通った道は全ての匂いと痕が消えていく。どちらに逃げたかを残させないため最後尾に配置された。アカルの次を歩くハナがいくつかの分かれ道で「良い方向」を示した。
ネムリは相変わらず眠り続けている。サキは、以前にオムナがネムリの頭に唇を当てたことを思い出した。あのときオムナはネムリを眠らせ続ける呪術を使ったのだ。そして、次にネムリが夢から覚めるのは、きっと、新たな土地にたどり着いた時だ。
8.いくさ
タカマのクニにヤマタの軍がたどり着いたとき、既にオムナはお宮の扉の前で控えていた。民衆も全てお宮の近くに集められていた。それまでに何匹もの臆病な獣が森で斬られるのをスズメは見た。それでも森はいくらか守られた。
ヤマタの軍の指揮者が馬から降りる。
「降伏の準備は万端というところか」
オムナが答える。
「そうではありませぬ。まず、その物騒な光る武具を捨ててもらいましょうか」
ヤマタの指揮者は大声で笑う。
「負けるのがわかっているからそのようなことを」
オムナが答える。
「そうではありませぬ。わたくしどもは、いくさを良しとしませぬ」
ヤマタの指揮者が満面の笑みで言う。
「では、降伏して我々の指揮下につくか?もちろん、お前は死ぬことになる。クニに主は何人も必要ないのだ」
オムナが答える。
「そうではありませぬ。あなたがたとわたくしどもは相容れぬ考え方。ここはお引取願います」
ヤマタの指揮者はまた大声で笑う。
「我らは更なる東を攻略することを目指しているのだ。それを引き返せとな」
ヤマタの軍がいっせいに武具を構えた。
「攻撃、来ます」
「ヤマタの指揮者はお宮を焼き払うつもりだ」
「お宮を焼き払うつもりでいらっしゃいます」
「こちらから松明を投げろとオムナに」
「松明をヤマタの軍にお投げください」
「民衆が何をすれば良いかとざわついています…痛い!」
あまりに多くの声を聞きすぎて、キキトリは苦しみ悶えた。ツクヨミはキキトリの頭に手をかざし、また唇を当てる。
「民衆も各々火を投げなさい」
「各々火を投げるようにとのことです」
「ヤマタの軍は火を投げる者たちと、武具で攻撃をする者に分けられました」
「女子どもをこちらに!」
「女子どもを洞内へ!」
民衆が投げた火に馬は慄き、混乱して落馬する兵が何名もヤマタに出た。馬は森へ逃げるものもあった。その途中でしかし落馬してもなお、ヤマタの民は自分に課された任務を真剣にこなす。火で攻撃をする者たちはまずお宮に向かってまず油を注ぎ、続いて弓で火を放つ。油で燃えやすくなったお宮はパチパチと音を立てて燃え始め、崩れ始める。オムナはその中でも動きはしなかった。ただ言葉を唱え続ける。
タカマの男たちは火を投げたり、お粗末な武具で攻撃をしながら、女と子どもをかばい、洞へと導く。しかしそれに気がつかないヤマタの兵がいないわけがない。
「そっちに何があるんだ」
幾人かの兵らが武具を手に洞へ向かった。それを阻もうとしたタカマの男が何人か斬り殺された。ツクヨミは岩の扉を開け、逃げのびてきた子どもや女の手を引き、中に入れた。
そして再び突き当たりに手をかざし縦穴を出現させると、キキトリに縄を渡した。
「お前はアカルたちの後を追いなさい。アカルたちの声を聞き取り、女子どもを数人だけでも導いていくのだ」
子どもや女たちは次々と縄から縦穴へと降りていく。まだ小さな男の子どもが1人、細い足で階段を下ろうとしたとき、子どもの背後で陰が動き、キラリと何かが光ると、子どもは鉄製の刀でひと突きにされた。洞内に血飛沫が飛ぶ。子どもを突き刺した刀を持った男が、ゆっくりと洞内に入ってきた。
「こんな隠れ家があったのか」
男は、刀に突き刺さったままの子どもを、洞の岩戸にこすりつけ、刀から外す。洞の入り口からは子の流す血がぼたぼたと流れ落ちた。
ツクヨミは険しい表情で声を張り上げる。
「コエ!お前もキキトリとともに行け!アカルたちに声を届けろ!」
コエは、一瞬スズメを抱きしめると、すぐに縦穴の奥に入っていった。
(さようなら)
その声はスズメの胸の辺りに聞こえてきた。
ツクヨミは再び手をかざし、縦穴に蓋をする。
ヤマタの兵はそれを見て「そっちに逃げたのか?どんな仕掛けだ」と、スズメを斬ろうとした。スズメはすばやくそれを交わす。ヤマタの兵が次々と洞の中に入り込んで来る。ヤマタの兵たちにツクヨミの姿は見えない。ヤマタの兵の目には少女が1人映るだけである。ツクヨミが青銅の剣をスズメに渡す。
「あの者たちにわたしが見えない以上、わたしはあの者たちと戦うことが出来ない。スズメ、最期まで戦え」
幼い頃から鍛えられ続けた理由はいくさの時のためでもあったのだ。スズメは深く理解した。
キキトリが泣きながら放った言葉「死ぬんだ」。「死ぬ」のは、自分なのだ。
サキがからかい半分に言った「スズメは、最期までツクヨミ様と一緒だよ」という言葉。
サキはあのとき、この時を先読みしたのだ。
鍛えられたスズメの肉体は、鉄製の刀に青銅の剣という分の悪さを抱きながらも、俊敏な動きで攻撃を交わし、同時に攻撃を仕掛けた兵を切り倒す。1人、2人、3人、4人目を切った瞬間、スズメの目に強烈な景色が映った。
「オムナ様…!」
その隙を、ヤマタの兵は逃さなかった。
ギラギラ光る鉄刀が、スズメを2つに切り裂いた。
どさり、どさり。
2つに分かれたからだは異なる速度で地に落ちる。洞内は血に満ちた。
生き残ったヤマタの兵は、半分になったスズメのからだを一蹴りしてから、洞を出て行った。
燃え尽きたお宮の灰の上でオムナは焼け焦げた姿となって倒れていた。
ヤマタの兵はそのオムナの焼け焦げた姿に更に火をつけ、森で斬った動物の肉を焼いて食った。そして酒の入った瓶を見つけて酒盛りを行った。
9.世界
真っ赤に染まった洞内で。
ツクヨミは2つに分かれたスズメの体を拾い上げ、慈しむように口付けをした。すると、スズメの体は真っ赤な砂に変わった。その砂を袋に詰めて衣服の中に入れると、ツクヨミは空に飛び、月に飛び乗った。丸く、青く、美しい水晶玉のようなこの世界。青い海と、緑の山々。木々の間を縫って流れるたくさんの川。
ヤマタのクニは滅びたが、森は生き延びた。森が生きている限り、この水晶玉が崩れることはないだろう。
アカルたちは水脈に沿って地下洞を歩いている。ときに休んで、また歩いて。
やがてキキトリとコエ、そして逃げ延びた子どもたちも追いついた。
サキが呟く。
「スズメは来なくて、良かったわ」
キキトリはスズメの最期の声を思い出し、泣き始めた。
「スズメが来ていたら、この逃げ道の最中でさえも、残酷な景色を見続けてしまったんだから。私たちのように、希望をもって逃げ続けることなんて出来なかったわ。だからあの子は…ツクヨミ様の元で最期を迎えて幸せだったのよ」
ツクヨミは、アカルたちがやがてたどりつくはずの地点に舞い降りる。
ネムリはサキの腕で眠り続けるまま。
新たなオムナは、オムナの死を背中の紋様に感じながら、旅の無事を祈る言葉をつぶやいた。
アカルたちが再びツクヨミと出会うとき、ネムリは長い眠りから目覚め、最初に呟く。
「ここから始まるの」