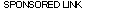白い焦性
山のふもとにある煉瓦造りの家。
私は、彼らとそこに住んでいる。
一見樹海にも見える鬱蒼とした木々に紛れた、すこし奇妙な平屋。
豪華さこそないが丁寧な造りで、ひたすら横に広くなっていて、
リビングホールを入れると全部で五部屋になる。
それぞれの個室の設計は、それぞれが好きなようにデザインしたせいで、
不規則に取り付けられた窓や出入り口が
外から見ると何ともいえない違和感を燻し出している。
その中にある、不思議な部屋。
扉も壁も床も天井も、光のように真っ白な八メートル四方の部屋。
目に見えるものは、ソファとギター、ターンテーブル、それにレコード。
それだけで、ほかには何もない。
余りにも用途がはっきりしているこの部屋に、
彼は倒れこむように帰ってくる。
「おかえり」
私はたいていこの彼の部屋で、勝手に酒を呷っている。
彼が教えてくれた、全然甘くないやつを。
向かって右の壁に寄りかかりながら、
中心のソファを見つめて。
「勝手に入んなって」
床に這いつくばりながらも目だけ動かして、彼は私を睨み付ける。
その目は、確実に酔っ払っているのにも関わらず、
銃弾みたいにまっすぐだ。
いつもこの目に殺される。
「そんなに嫌なら鍵かければいいじゃない」
「めんどくせえ」
彼はそう吐き捨てて、寝返りを打ち天井を見上げた。
長い黒髪、土気色の顔、細い腕、高い背、枯れ草のような声。
真っ黒なスーツに、真っ黒なライダースジャケット。
どこをとっても不健全な彼はこの部屋にぴったりだ。
あらゆるものを嫌うくせに、たまらなく寂しそうな彼と、
この部屋はよく似ている。
「酒」
腰を上げ、歩み寄り、緑の瓶を差し出した。
半分程度残っていた中身を仰向けのまま空にすると、
彼はゆっくり起き上がり、
割としっかりとした足取りで、左の壁に近寄っていった。
ターンテーブルの前に立ち、
しばらく止まり、
目の高さに作りつけられているレコード棚から
目当ての一枚を取り出した。
レコードに針が触れる音がするとまもなく、
ひずんだ音がどこからか聴こえてくる。
彼がかけたのは60年代のパンク。
きっとまた、どうしようもないことでもあったんだろう。
「なんかねえの?」
「何が?」
「酒」
ないなあ、と答えると、彼は舌を打って、
もう一度瓶を逆さまにした。
本当は、ないわけでもないのだけれど。
それから何も言わずソファに腰を下ろすと、
彼はゆっくりした動きでポケットを探り、
煙草とライターを取り出した。
なかなかつかない火にいらつきながらも、
ようやく燃えはじめたそれをふかす。
灰色に揺らぐ煙の中で白い扉を見ているから、
黒目まで白く見えた。
この部屋には窓も換気扇もないから、
煙はすぐに満ちていく。
「秋に死ぬ鳥の話ってしたか?」
「してない」
煙草とお酒の相乗効果で、饒舌に語りだした彼は、
愉快な話でもないのに、身振り手振りを加えながら、
それはもう楽しそうだ。
ただ少しだけ、虚ろな目をしている。
「その鳥は秋に生まれんだけど、
その時にはもう親鳥はいねえの 死んでんの 巣の中で
で、初めて見る親鳥の死体から、悟るわけ
自分もこうなるって
でもその鳥は生きるしかねえわけじゃん
だから生まれてからすぐ、飛ぶんだよ 餌探しに
そんで一日もしないうちに鳥としては完成するんだぜ
空飛んで 獲物喰って すげえ満ち足りる
でもそれからどの季節もたった一回だけ経験して、
また秋が来て、死ぬ一種間くらい前に卵生んで、
暖め終わると同時に死ぬ そんな鳥
悲しいだろ?」
「悲しいかなあ」
「いや悲しくねえけど」
「悲しくないじゃん」
「だっていねえもん そんな鳥」
「いないの?」
「いたら悲しいだろ?」
「そう?羨ましいよ」
彼は、黙って煙草を瓶の中に落とした。
湿ったアルコールの匂いがする煙が、ゆらゆら立ち昇るのを見届けて、
ゆっくりと目を閉じ、やがて呼吸が整い、名前を呼んでも返事をしなくなった。