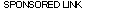カッフェ
氷が水に変わることで、時間が過ぎたことを知る。
午後二時の喫茶店は、まだ溢れかえっていた人の気配を残していた。
店全体が通りに面している古い造りの店内で、流行の歌が右から左へ。
久しぶりの晴れた空からの刺すような日差しと、私は少しうたたねしていた。
フレーバーティーのグラスから、また音が響く。
「ごめん 待ったでしょ、待ったよね?」
空回りする会話を始める彼を、私は待っていた。
色白の、ひ弱そうな体いっぱいに汗をかき、息を切らしている。
外はまだ夏のように暑い。
「何か頼む?ええっと、コー・・」
「ううん、いらない 飲みきったら頼むから」
「そ、そう じゃあ紅茶を、アイスで」
アイスティーですね?と聞き返され、
焦っている彼を心の中で毒づく。
(そこで戸惑ったら、フォローになってないじゃない。)
意地悪で、少しの悪意と初恋に似た気持ちを、微笑ましく思っている。
「初めて話したとき」
「え?」
「コーヒー、苦手だって言ってたよね」
「え、言ったっけ、そんなこと」
私は場の空気が読めない人間が嫌いだった。
その人がいるだけで、なんとなく波風が立つような気がして。
彼はそれを体現しているような人だった。
おどおどして、落ち着きが無く、いつも運悪く人の粗を見つける。
良く言えば純粋。
だけど私はその中に、悪意が垣間見える気がしていた。
「言ったよ 苦くて喉につっかえる感覚が嫌いだって」
「いや、そんなことないよ あの、苦味が・・・・・・」
私はコーヒーが好きだった。
小さい頃からコーヒーに憧れていた。
彼と初めて会った頃だったろうか、漸く「おいしい」と思えるようになった。
だからこそ、それまで無口だった彼の何気ない一言が頭に残ったのだろう。
「無理、することないと思うよ」
「そうじゃないんだ」
「そのまんまでいいから」
「ぼ、僕は」
しつこいようだけど、私は滑らかな会話のできる人を好むから、
未だ会話を詰まらせる彼を嫌うことのほうが容易いはずだろう。
それでも、彼はなんとなく受け入れてしまう理由が、
きっとどこかにある。
「君と、もっと・・・」
アイスティーが運ばれてきた。
先ほどのウエイトレスが、失礼しますと彼の前に置く。
時が過ぎるのに似た音がした。
それは私のグラスと共鳴する。
「それ、何のジュース?」
「これ?」
「うん」
「いちじくのフレーバーティー」
「へえ、珍しいね」
表情が、ふと緩んだ。
つられて笑ったのは、私にも緊張があったせいだった。
「いちじくって」
「うん」
「君を果物にたとえるなら、いちじくだね」
「それ、喜んでいいの?」
一瞬困ったように見えたけれど、
私の前で彼はたいていこんな顔だ。
気の毒な気にも、もっと困らせたいような気にもなる。
彼と向かい合うことで私が彼を映しているのだとしたら、
彼の中には、私の知らない魅力があるのかもしれない。
「いちじくってどう書くか、知ってる?」
「ううん」
「無い花の果実って書いて、無花果」
水の線をテーブルの上に引く仕草が滑らかで、
細い指に見惚れてしまった。
こういうことのある度、彼の魅力は末端にあるのだと感じていた。
指の先、睫毛の先、言葉の先。
見つめた瞳の奥先。
気恥ずかしいようで、彼はすぐ隠すけれど。
「でもね、無花果って言うのは本当は、花の実なんだ」
「へえ」
「無花果の花は、実の中にあって」
「うん」
「みんなが食べてるあの実は、じつは花なんだ だから」
「・・・だから」
「君に、似てるよね」
無造作に手にとって、フレーバーティーを飲み干した。
視線は一つの像を結ばない。
彼の瞳の奥を、探ることもない。
「あ」
「なに?」
「今、少し顔が赤いよ」
喫茶店の中に流行の歌が鳴り響いて、
グラスの音よりも私たちを色濃く染めた。
それは案外、居心地の悪いものでもない。
「もう、行かない?」
「そうしよう」
涼しかった空間を通り抜け、
蝉の声が聞こえる。
頭はぼんやりと、空気は柔らかに。
彼の呼び止める声に振り向いた。
「今度こここに来るときは」
後ろにいる彼の表情は、逆行でよく見ることが出来ない。
ただ子供たちが笑いながら傍を通り過ぎるほどの間、
互いの顔を見合っていた。
「コーヒー、飲めるようになるから」
笑って答えたあのときが、
この日、一番の真実だった気がした。
「今度は、コーヒーをホットで二つ、ね」