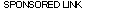親指の味
いつも淡い光が、その人の手や肩の周りなんかを優しく象っていた。
決してうっとうしくない、存在感のある色のついた光は、その人を太陽みたいに見せていた。
その人はよく親指を噛んだ。
爪は噛まなかった。爪のはりつく指先の皮膚を、暇さえあればがじがじとやっていた。
爪はいつだってきれいで、噛んだ後の行動パターンはいつも同じ。
ふやけて穴が空き、醜くなったその親指を、私の鼻先につきつける。
私は唾でてかてかと下品に照る光とその人から発せられる上品な甘い光を同時に見ながら、表情を変えない。
その日の空は青い。
深く奥行きのある明るい青に、スズメが自由な延長線を引く。
私とその人は、アパートのついでみたいに取り付けられた狭いベランダで、エアコンの空気を交換するでかい機械(その人もこの機械の名は知らなかった)に並んで座っていた。
身体を波のように重く長く揺らすと、軽く心地よい、罪悪感を誘われるような素敵な音がする。
機械は動いてはいなかった。まだ春先で、エアコンをつけずとも我慢すればなんとかなるような気温だった。
今日のその人の光は、今まで見た中で一番強く自己主張していて、ライオンのたてがみを生やしたようだ。
控えめで、見られたくないのに見えているというようなこれまでの光ではない、堂々とした意思を持った生き物のように、耳を澄ませば光の息遣いが聞こえそうだった。
「ね、噛んでいい」
ずっと近い上空を、今にも粉砕しそうなくらい貧弱なプロペラを廻しながら、ヘリコプターが弱い遠い音を立てていた。
その人は私の親指をずっと見つめていたから、そろそろこんな台詞が来る頃だろうと思っていたところだ。
私は唇をすこし曲げた。
「気持ち悪い、そんなの」
その人は私の左手をとり、親指を探し当て、舌先で爪を下から上へ一回舐めた。
神経の無い爪に伝わる柔らかな肉に撫でられる異様な感覚は一瞬で消えた。しかし後に残る感覚だった。
ヘリコプターの音は無限の空へ消えていく。
私は親指の爪に残った唾液をその人の麻の服で乱暴に拭いた。
染みもできないくらいに少量の唾液だったが、私は確実にその行為に対してぞっとしていた。
やたら気色悪かった。
その人はすぐに親指の先の皮を噛み始めた。
泣き止みかけている子供の動作みたいに見えた。いとこに2歳の男の子がいたが、こんな仕草はしたことがない。でもしているところなら簡単に、とても鮮明に想像できた。
私のうつむきがちな視線から見えるその人の膝は、相変わらず黄色い光を放っていた。
何故だか、少しだけほっとした、変わっていないことが嬉しかった。
やがて結果を報告するように、そのひとの親指が鼻先にのびてくる。
いつもより眩しいその人工的ともいえるほどくっきりとした黄色に対してしかめた顔は、その人からは見えない。
それもまた私に安堵を与えた。いつもはこういうときに無表情だから、表情を変えたことが知られると、負けたような気持ちになるに違いないなという私の意地の気持ちからだった。
「もしかしてポテト、食べた?」
私は眩しさに眼をそむけ、成長したたんぽぽの茎くらいにかたくした表情をその人に向けた。
「食べてない」
「塩の味がしたな」
濃く黄色く焼きあがった、たっぷりとした油を含む、細いポテトを想像した。そしてそれがたまらなく食べたくなり、自分の親指を舐めた。
ろうそくを舐めたような気がした。
私はその人と会う前、塩味のポップコーンを食べていたことを思い出した。
私はその人を勝ち誇ったように見た。その人だけが持つキレイな黄色い光を横取りできたような気がした。私は浮かれた。
ポテトだけが塩を使った食べ物ではない。私は勝ち誇った。