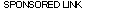あいしてるのこえ
あまりにも太陽が元気に照りつけるものだから、
僕は半ば朦朧としていた。
彼女もきっとそうだろう。
そんなほろ酔いにも似た気分で海辺を歩いているときに、
彼女は言ったんだ。
「ねえ、これだけ日が強かったら、
この石も銀色に見えるかしら」
僕が戯れにプレゼントしたそれを太陽に掲げて、
愛おしそうに眺める彼女を、
僕は愛おしそうにみつめた。
長い黒髪を風になびかせる彼女が好きだったから、
一昨日ばっさりと切ってしまったときは、
本当に少しだけど愕然とした。
だけど、見慣れないはずのショートカットも、
彼女にはよく似合っている。
白いワンピースも似合うままだ。
僕が彼女に求めるものはそれだけだった。
だから今日も相変わらず、僕は隣を歩いている。
「そっちに行くと、危ないよ」
ふらふらと波打ち際によって行く彼女を引き止める。
向かうのは、いつも翳っている洞窟。
そこで裸になって、ただ僕らは二人で並んでいるんだ。
何が楽しいわけでもないけれど。
「ねえ」
「なに?」
「悲しいわ、わたし」
僕らの背中には、ひどく大きな火傷がある。
違うときに、違う場所で、場所も細かには違うけれど、
共通しているのは誰かに傷つけられた跡だということ。
あやふやな親近感、恋にも似た気持ち。
それが僕らのそばにいる理由。
傷をなめあうことが目的じゃない。
僕らの関係はむしろ、
もっと深く、深く傷に入り込んで、
細胞を見詰め合うほど自棄的でロマンチックなものだ。
「脱ごうか」
その一言も艶すら持たない。
何の恥じらいもない。
洞窟の中で、にわかにこだましたとしても。
僕らには、もっとセクシャルなサインがあるからだ。
何も言わずにワンピースをたくし上げる彼女を見ながら、
彼女が入り口でつぶやいたあの言葉の意味を考えることにした。
彼女がしゃべらなくなったときの、僕のかわいい癖だ。
あの太陽から、
溢れかえる人から、
自分たちの劣等感から逃げるように、
暗がりで背中にもたれ掛かりあう。
そんな瞬間を、彼女は悲しいと言ったのだろうか。
いやきっと、違うはずだ。
「明日わたしがここにこなかったら、あなた、どうする?」
出し抜けにつぶやかれた問いには、もう答えが用意されていた。
それは偶然にして必然だった。
だってそんなことを考えない日は、なかったから。
「ずっと君を待ってるよ」
いつものように、ずっと。
雨が降っても、嵐になっても、もしこの洞窟が竜巻で壊れたとしても。
僕は、君を待ってるよ。
君に伝えられなかった僕の思いを全て込めたつもりで、言った。
「それが聞きたかったの」
もたれあうのは背中だけのはずなのに、
今日の彼女はとても温かい。
僕の肩の上に置かれた頭から、
握られた左手から、
彼女の脈が伝わってくる。
少しだけ早い。
そして顔も、少しだけ赤い。
夕日のせいじゃないことがなんとなく照れくさくて、
そっぽを向く僕に、少し呆れた吐息。
少しの間だけ、心臓がじんと熱くなる。
「うん 待ってる」
僕は、彼女が明日来ないんじゃないかと思ってる。
でも確かめ合うようなことはしない。
彼女がもし世界からいなくなったとしても、
僕はここで彼女を待つのだから、
聞いたところで仕方がないことがまず一つ。
もう一つは、僕に確信があるからだ。
彼女はきっと、あの石が銀色に輝く、
この海辺に帰ってくる。
何故なら銀色に輝く光だけが、僕らのセクシャルなサイン。
「あいしてる」という意味の、キスのような光。