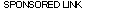ティーポットフィッシュ
ティーポットフィッシュ
この透明なティーポット越しに見る景色は驚くほど退屈だ。
これならいっそ陶器製の物で真っ暗闇になれば、前に居た世界を忘れる事ができたかもしれない。
しかもご丁寧にヴェネチアンガラス工場の限定品。
小さな月と波の光の反射も、とても美しく映し出すガラス製品。
...嫌味としか考えられない。
足元にはコロコロと転がる綺麗なビー玉。
水草の代わりに牡丹茶の茶葉が一つ。(これはかなりこだわったお茶で、
中国の茶葉が花の形のように紐でくくられていて、見た目を楽しむお茶だという)
お茶の色は水と上手く分離していて、半分から上がお茶の緋色。
半分から下はただのカルキ抜きの水で、水面に顔を出す事もままならない。
この中の水は恐ろしく清潔で規則正しいけれど、
本当はこんなの本物じゃない。
ティーポットのガラスと、
その先の船の窓ガラス越しに見える大海原。
きっといつか還れるんじゃないかな。
恐ろしく不潔できまぐれな波しか立てないけれど。
干からびたような身体をいっぱいいっぱいに広げて、
ここぞとばかりに泳ぎ出せたなら。
所詮は夢。
夢は夢の中で夢で終るものなんだ。
「そんなに恨めしそうな顔をしていないで、こちらへ出てきてごらん?」
ふと声のする方を向くと、久方ぶりの満月が居た。
その満月の光が声となって、水とガラスの振動でティーポットの中まで届いてきたのだ。
このような場合挨拶を返すのがスジだろうけど、
生憎そんな丁寧な社交辞令は守れない。
「いい気なものですね。あなたは外に"居っぱなし"だからそんな風に言えるんだ。」
満月の言葉が少しかちんときたので、不機嫌そうに返してやった。
でも満月は怒らないんだ。
それはこの世界に住む住人はみんな知っている。
「少し出てくればいいじゃないか。それともそのティーポットで一生過ごすのかい?
文句をつらつらと並べる前に、少し動いてみたらどうだい?」
満月は怒らないけど結構意固地なんだ。
これもみんな知っている。
一度言い出したら聞かないし、自分の意見は死ぬまで通すタイプなんだ。
「でも...そうは言っても満月さん、もう泳ぎ方なんて分からない。
このまま海に還って泳げないなんて!海に受け入れられないのと同じだよ。」
怒ったつもりで吐いた言葉なのに、
気付けば視界が丸く見える瞳からは大量の涙が流れていた。
...涙がこのまま沈んで真珠になればいいのに。
その瞬間、綺麗なビー玉は酷く貧相に見えた。
ティーポットの中で初めて流した涙だから、
そのくらい綺麗に見えてしまった。
「おやおや、泣く事はないよ。
君は少しその中で臆病になってしまったんだね。」
「臆病...?」
そんなつもりはない。
だって、今までずっと一人で生きてきたのだから。
「信じたものを見失った"だけ"だよ。
さぁ、泳ぐのは忘れるんだ。」
満月は急にはりきった声色になると、
その光をティーポットにキラキラと向けてきた。
ティーポットの置いてある船室の窓は薄いから、
思わず窓が割れるかと思ったくらいの大きな光だった。
「泳ぎ方を忘れたなら、飛んでみるといいよ。」
一瞬のうたたねの間に見るような夢の感覚といえばいいでしょうか。
それが過ぎ去ったように、ティーポットの中には綺麗な真珠が残りました。
そして船の周りはにぎやかな水の跳ねる音がしていましたが、やがて遠くなっていきました。
次の日。
その真珠のティーポットが置いてある船室に、
綺麗な夜色のドレスを着た女の人が入って来ました。
ゆっくりとした動作で古い木製の椅子に腰かけると、ティーポットを覗き込みます。
キラキラとたくさんの宝物が光るのを確認すると、ティーカップにそのお茶を少し注ぎました。
ガラスのカップの底から昨夜の涙が浮かんでくると、彼女もまた涙を流しました。
「よかった、やっと元気になったんだわ。」
海の宝物味ブレンドのお茶を一口すすって、
来月には元気な笑顔で出会えることを期待するのでした。