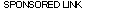桜
駅を出て踏み切りを渡り、線路脇の細い道を少し上ると小さな郵便局の前に出る。それから左へ、今度は緩やかに下る長い坂道を行くと、しばらく先でその道がまた上りと下りに分かれているのが見えてくる。
目の前を歩く母の髪が、マフラーのせいで奇妙に盛り上がり、ねじれて絡まっているのが気にかかる。でもきっと、手櫛で直そうにも直せないだろう。わたしはその中に、何本もの強情そうな白髪をみつけて少し悲しい気分になった。
「ここにほら、小さな沼があったの、覚えてるよね?」
母が坂の左手に顔だけを向けて言った。
覚えている。
今は新しい家が建ち並んでいるけれど、確かにそこは沼だったところだ。その沼の隣には、当時すでに閉園になっていた小さな幼稚園があって、寂れた園舎が斜面に沿って建っていた。
通りから見下ろすと軽く飛び降りられそうなその緑の屋根は、春になるとピンク色の花びらで染まった。その辺りを含め、坂の上の雑木林だった場所には今、大きなマンションが建ってる。
まだわたしが小さなころ。
たくさんの貼り紙やたて看板がマンション建設を反対していた。もちろんその時には読めなくて、ただ絵のような赤や黒の文字たちの最後に、必ず「!!」がついているのが可笑しく思えていた。
それから・・・
「それから久美・・・覚えてる?」
母が探るように言う。
「覚えてる覚えてる。わたしと啓太郎が沼にはまってさ・・・」
母が思い出させようとする何かを避けるように、わたしはわざと違う(と思われる)ことを口にした。
小学校の二年生になったばかりだったわたしと幼なじみだった啓太郎は、ザリガニを釣ろうというひとつ年上のお兄ちゃんたちにくっついて、「絶対に行っちゃいけない」と言われていた沼に降りた。降りてすぐ、啓太郎の左足が沼にはまり、それを助けようとしたわたしも落ちてしまった。
落ちたと言ってもほんのすぐそこの浅いところで、いくらでも自力で上がれたのに、お兄ちゃんたちは「底なし沼に落ちた!」と大騒ぎで親を呼びに行き、残されたわたしと啓太郎は動いたら終わりなんだと、手を握り合って泣いたのだ。
「そのあんたたちが、結婚なんてねぇ・・・」
「でも、あれからずっとくっついていたわけじゃないし」
小学校の間は一緒だったけれど、啓太郎は私立の中高一貫校から地方の大学へ行ってしまい、その後社会人になって戻ってきた彼と再会してつきあうようになったのは、つい三年前のことなのだ。
ざっと、15年のブランク。
「それにね、お母さん、啓太郎ったら沼にはまったこと、全然覚えてないの。もう、病的に記憶力がないんだから」
「でも、久美のことは覚えていたのでしょ?」
「さぁ、どうだかぁー」
同窓会で再会した啓太郎は確かにわたしを覚えていたけれど、覚えていることと忘れずにいることでは、どこかが違うような気がする。道端ですれ違っていたら、どうだったんだろう。
「変わったわね、この辺」
母はそう言って立ち止まった。ちょうど雑木林のあったあたり。
「そうだね・・・」
母はここで、わたしになにかを思い出させたいんだろうか。それとも覚えていないことを確かめたいんだろうか。坂の上の方を見上げて黙っている。
「雨が止んでよかったね」
わたしはそう言いながら母の横顔を見た。母の目の先にはマンションの外階段が横に広がっているだけだ。昨日まで雨続きだったせいか、玄関先に傘を広げて干している家がある。
でもきっと、母はちがうものを見ている。
きっと、もっと遠いところ。
父の転勤に伴いわたしたちがこの街を離れたのは13年前、わたしが15の時だった。
両親は7年前に離婚して父は新しい家族を持ち、わたしは母とふたりだけで暮らしてきた。
今日は啓太郎の家に招かれて久しぶりにこの街に訪れたが、沼の反対側の小さな丘も切り崩されて家が建ち並び、当時の面影はほとんどない。
面影はないけれど、わたしにはまだ鮮やかに思い出せてしまういくつかの情景がある。
啓太郎と沼に落ちたことも含めて、幼い頃の記憶の断片は、全てこの場所と繋がっているのだ。
そしてそこには母がいる。今よりも若く美しかった母が。
最初の記憶はたぶん、幼稚園にも上がるまえのことだ。
雑木林の中、舞い落ちる花びら、無心にそれを拾うわたし。
すぐそばに母の足が見えていたから、わたしは安心してその場にしゃがんでいた。そのうち靴音が近づいて、母のそばにもう一組の足が並んだ。底の厚い、紐付きのごつい靴を履いた足だった。
父ではなかった。
ふたりは長い間、密やかに親しく話をしていた。目の前に見えていた紐靴と母の華奢なサンダルは、わたしの小さな両手でそれぞれに触れられるほどに近かった。
それは一度だけのことではなくて、わたしが小学校に上がるまで何度かあったような気がする。
少し先に雑草だらけの幼稚園の庭が見えていて、錆びて色あせた遊具たちはそれでも充分魅力的だったけれど、とげとげの針金が張り巡らされているから、中には入れそうもなかった。
だからわたしはいつも、母のそばでしゃがんで遊んでいた。
園庭の向こう側には沼があって、かすかに湿った臭いがしていた。
母とその人の話し声は静かだったけれど、ときどきの笑い声は柔らかくほどけるようにふわふわと、しゃがんでいるわたしの上に降りてきた。わたしはなぜか、頭上を見ることがいけないことのように思えて、ただずっと花びらを拾い集めていた。拾っても拾ってもそれは目の前に降りてきた。
ある時、その人の靴の紐がほどけかけているのに気がついて、わたしは花びらを拾う手を止めた。
おずおずとその手を伸ばし、直してあげようと触れたはずのその蝶結びは、けれども、わたしの指先でするするとほどけてしまった。どうしようと思ったとき、
「ありがとう、久美ちゃん」
いつも高いところで母に向かって発せられていた声が、初めてまっすぐわたしに向かって降りてきた。
慌てて母の足の後ろに隠れると、その人もしゃがんで、魔法のように素早く靴紐を結び直した。
「直してくれようとしたんだよね? ありがとう」
はじめて自分の目の高さで見た紐靴のおじさんは、思っていたよりもずっと若くて、何かわからないいい匂いがして、樹木の香りが急に濃くたちこめたような気がした。 それからおじさんはわたしを見て、もう一度「ありがとう」と微笑んでくれた。
その目が少しだけ悲しそうに見えて、なんだか、「いっしょにあそぼう」って言えないで、みんなの輪の外からこっちを見ている子の目に似ていて、でもわたしは、自分から声をかけるなんてできなくて・・・だから、すぐに目をそらしてしまった。
本当は、分かってくれたことが嬉しかったのに。叱られなくてほっとしたのに、わたしは頷くことさえできなかった。
ただ、初めて聞いた「ありがとう」の響きを、心の中で何度も繰り返して温めた。
おじさんの言ってくれた「ありがとう」は「とう」のところにアクセントのある「ありがとう」だった。
紐靴さんが誰なのか、母のなんなのか、その頃のわたしに分かるはずもなかったし想像もできなかった。
小学校に上がる頃には、わたしはおじさんに会うことはなかったと思う。
そうして、啓太郎と一緒に沼に落ちた日が、わたしの中のおじさんの記憶の最後の一枚になった。
あの日、わたしは沼の真ん中近くにぽかりと浮かんでいた紐靴を見たのだ。
底が厚くて無骨な、見覚えのある紐靴の片一方だけを・・・。
それは、後からはめ込んだ映像のような気がしてくることもある。
あの靴を取って欲しいとわたしが言い、無理だよと言いながらバランスを崩した啓太郎が沼に落ちた。落ちたのは事実だから沼の臭いも感触も覚えているけれど、そのきっかけの靴についてはいつも、本当にあの紐靴だったかどうかわからなくなってしまうのだ。
なんせ、啓太郎はなにも覚えてくれていなのだから。
「久美ってさ、想像と記憶をごっちゃにするところあるよな」と、啓太郎には言われたことがある。
しゃがんでいるわたし。一面の花びら。母と紐靴のおじさんの足。ごつい靴、話し声、笑い声、おじさんの悲しそうな目、沼、花びら、花びら、花びら。
今さら勝手に組み立ててみても、おそらく正しくは繋がっていかない記憶。バラバラでありながらどれも外せない、淡い色のついた映像の断片たち。
それのどこまでが本当なんだろう。
たとえば誰かが、幼い頃に一度見ただけのある人の悲しそうな目が忘れられないのだと言ったら、わたしは「きっとそれがあなたの初恋だったのね」と思うだろう。
そう。たぶん、それは正しい。
わたしはおじさんの悲しそうな目に、なぜだか強く惹かれた。おじさんの言った「ありがとう」に惹かれた。
だからこそ、おじさんといる時の母を好きだと思えたし、ふたりと一緒にいる時間が好きだったのだろう。
その一方でわたしは、おじさんの存在がわたしを、わたしたちを不安定にしているということにも、本能的に気づいていたような気がする。
沼に放られた靴は、その象徴だったのかもしれない。
わたしの記憶が正しいにしろ、正しくないにしろ。
母が離婚をしたとき、した後、わたしは紐靴のおじさんのことを時々思い出した。どこからかまた母とわたしの前に現れるのではないかと。
けれどもわたしの知る限り、そういうことはなかった。
やはりおじさんはもう、沼の底なんだろう。
もちろん、限りなく比喩的な意味で・・・。
「おーい」という声がして、坂の上から啓太郎が大股で歩いてきた。
「遅いからどうしたかと思ったよ。今日はわざわざすみません」
後半は、母にぺこっと頭を下げて言った。
「つい、懐かしくて立ち止まってしまっていたの。お待たせしてごめんなさいね」
「いえ・・・でも、ずいぶん変わったでしょ? この辺も」
そう言って、啓太郎も母と同じように空を仰いだ。
「覚えてるの? 啓太郎、信じられないくらい記憶力ないのに?」
わたしは少しちゃかしてみた。
すると、
「忘れないことだってあるわよね」
と、母が言った。
「忘れられないことじゃなくて?」
「そう、忘れられないことじゃなくて、忘れないこと」
母はこの場所で、わたしになにかを話したかったのかもしれない。
でも、わたしはなにも聞かなくていいのだ。
たとえわたしの記憶が母の持っている記憶と違っているとしても、
わたしは覚えている。
母や啓太郎に倣って、わたしもマンションの外階段のあたりを見上げてみた。
踊り場に広げて干してあったピンク色の傘が、つつつと風に押されて動いたけれど、舞い上がったりはしなかった。