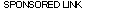ベンチ・オンリー・パーク
ここ数日の小雨は気付けば止んでいた。
しかし雲は不機嫌そうにたれこめている。
風と時間が同時に流れる午後に、
ノートを書く意味を失った。
投げ出した手足を納めるわけでもなく、
さらに窓の外へ視線を投げ出して、
今朝聴いて来た音楽を、少しずつ思い出していた。
いつもこの席から見えるあの場所は、今日も見える。
どうしてあの場所にこんなにも惹きつけられるのだろう。
用水路の傍らに連なる、梅の木の向こう側。
ベンチだけの公園。
「斉藤」
「はい」
「受ける気がないなら、出て行っていいぞ」
「わかりました」
静まり返った教室と、
生徒いびりが趣味の教師と、
従順なクラスメート。
置いてあるだけの机と椅子。
張ってあるだけのガラス窓。
整頓された空間。
どれもこれも、ここにいる意味なんて成さなかった。
幅1.6mほどの廊下はとても秩序だっていて、
足音を消して歩くと空気になった気分だ。
右にはいくつもの部屋が同じように収まっていて、
そういうものを見ると、何故か吐き気がした。
無遠慮に胃を鷲づかみにされたような吐き気。
校庭を囲むようにコの字型に設計された校舎の、
真ん中が二年棟で、
その後ろには体育館やらプールやら、もろもろの施設が横に並んでいる。
そのまた後ろにある用水路を越えた場所に、公園はある。
二年棟を貫く昇降口から裏へ出ると、
コートも羽織らない制服姿では寒さが体に沁みた。
でも少しだけ高揚していた私には、
これぐらいの冷たさがちょうど良かったのかもしれない。
「さむ…」
すると左の壁側から声がした。
「斉藤さん?」
「…山内くん?」
うずくまっている人影が、
彼だとわかるためには時間がかかった。
この山内くんは稀に見る秀才として有名で、
学校にはめったに来ないのに、
テストでいつも全教科満点をとるという嘘のような人だ。
私はそんな人と、席が隣だということもあって、
時折趣味の話をするような仲だった。
確か今日は、来ていなかったはずの彼と、
こんなところで会うなんて思いも寄らなかった。
「何してんの?」
「山内くんこそ」
「俺? 俺はほら…不良ごっこ?」
彼を知っていればこそ、
思わず笑ってしまいそうな台詞なのに、
彼の周りに落ちている煙草の吸殻を見ると、
それも冗談ではなくなりそうだった。
しかしその時の彼には少しも違和感がなく、
私はとても不思議な気持ちだった。
「斉藤さんは?」
「私は…、探検」
それに比べて、
余りにも違和感のある私の答えに、
私と彼は顔を見合わせて笑った。
彼は新しい煙草に火をつけながら、
私のほうを見ずに尋ねる。
「目的は?」
「公園」
「あったっけ、この近くに」
「うん、向こうに」
私の指差した先は、ちょうど彼が視線を向けていた先で、
彼はさも面白そうに笑うと、つけたばかりの煙草を足でもみ消した。
「俺もついてっちゃお」
どうして彼がそんなことを思ったのかは判らないけれど、
彼のその言葉に、心が少しときめいた。
「つまらないかもよ?」
「その時は、斉藤さんに責任とってもらうから」
「どうやって?」
「セックス」
今朝聴いて来た音楽が、
フルボリュームで頭の中を突き抜ける。
私なんて消し飛んでしまいそうな音楽。
そして無意識のうちに、笑っていた。
「じゃ、いこっか」
これは賭けだ。
それも綱渡りなんて頼りないものじゃない。
私は橋を渡るんだ。
確かな足取りで、決して止まらずに、
こんなところを超えた場所に続く、
彼という橋を渡る。
「斉藤さん?」
「なに?」
「いいの?」
「いいの」
「いいのか」
「いいのよ」
そしてまた顔を見合わせて笑い、
私たちは縦一列になって歩き出した。
静かな追い風のせいで、彼の煙草の煙が肺に入る。
扇情的なノスタルジア。
遠くに見た雷鳴。
一握りの運命。
私たちの歩いた時間は、束の間のロードムーヴィーのようで、
用水路に着いた頃に、雲の切れ目からは青い空が見えていた。
「斉藤さん」
「うん」
「これは無理だね」
「そうね」
遠くから見ていた用水路は思いのほか広く、
そこには綱も橋もないし、渡るのは不可能だった。
ただ、これでいいような気もした。
ここから見るあの場所は、
変わらずに惹きつけられる場所だったから。
「ああ」
「どうしたの?」
「虹が架かってる」
その虹はまるで、
ここと公園を繋ぐように架かっていた。
彼もそう思ったのだろう。
「あの虹、渡れるかな」
「渡ろうと思う?」
しばらく考えて、ふ、と笑った時の彼を
私は忘れない。
「いや、別にいい」
綺麗だなあ、と彼が言って、
そうね、と私が相槌を打って、
一瞬触れた手を、そっと繋いだ。
そして虹が消えるまで、しばらくそこに立っていた。